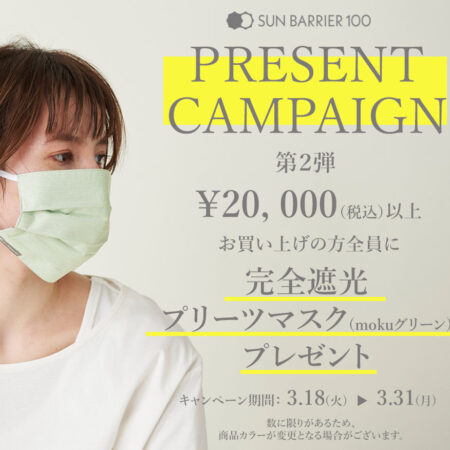2010.12.30 | 岡ちゃんのぐだぐだコラム
2010年1月~12月
■2010年の終わりに
ホノルルマラソンを一度完走(完歩)すると、もう何でも歩いてやれという気になり、マウイマラソンも乗鞍マウンテンサイクリングもほとんど歩いて完走している。そして、ホノルルマラソンに入れ替わった人生の三大目標のひとつモナコグランプリに行けたのは今年のハイライトやった。モナコに3泊5日で行けるとは思いもよらなかったし、何よりもマイル通の友人のおかげでちょっと贅沢な国内旅行くらいの予算で思いもかけず長年の夢がかなった。F-1ファンなら誰もが夢見るモナコであるが、こんなにすぐ叶うとは思ってもいなかった。少しのお金と必要な体力、十分な気力、そして何より仲間の存在が大きい。小学校の下校時、いつも車の話をしながら帰った同級生が今年他界した。生かされている人生を出来るだけ活かすのが使命と勝手に遊びの言い訳をしているが、顔をしかめて走るだけが人生ではないと思う。よく遊びよく学ぶ、よく遊びよく仕事する。やっぱりこれやね、と思う。今年も1年ありがとうございました。来年はどんな年になることやら。
2010.12.30
■マラソンシーズン
12月になるとやはりホノルルマラソンが気になるのと同時に「人生の目標」に「ホノルルマラソン完走」を掲げていた頃を思い出す。しかし、学生時代から長距離走が何より嫌いであった俺にフルマラソン完走など夢のまた夢と思っていたことも事実で2000年から参加している友人に誘われ四半世紀ぶりにハワイに行ったときもマラソンではなく10kmのウォーキングに出た。そしてそのとき、多くの日本人が「絶対に歩かない」とか「去年よりタイムを縮める」とかいう意気込みで必死の形相で走っているのに比べ、最初からフルマラソンを楽しそうに歩いている欧米人たちに驚き、触発されその後フルマラソンを歩くきっかけとなった。ホノルルマラソンは折り返しのコースなのでよく分かるが、後半になって悲壮な顔でフラフラになっているのは決まって日本人である。苦しむのも楽しむのも個人の勝手やけど、何をやっても一所懸命になるのは日本人のエエとこでもあるし、悪いとこやとも思う。いつも先を急いで走っていると見えない景色も歩いていると違って見えるっちゅうのも面白いところで、マラソンが人生に例えられる所以やと思う。
2010.12.29
■国産比率
ちょっと考えるところがあって、これからは身の回りのモノは出来るだけ国産比率を高めようと思っている。そしてそれなら国産比率の低いところから始めるべきと思い、色々考えてみると、まず、衣料品の国産比率が低いやろと。生活圏内にユニクロが出来てからというもの、オン・オフを問わず、それこそ頭のてっぺんから足の先まで着るものはすべてユニクロということも珍しくない。さらにカバンやサングラスまでユニクロであるから国産比率ほぼゼロ、中国比率100%ということになる。これではいかんやろと思い少しづつ国産品を増やしているが、値段と品質のバランスを考えるとこれは中々難しい。それでもシャツはこの頃鎌倉シャツを愛用しているし、これまた近所に出来たアウトレットのおかげでBARACUTAのスイングトップやジャケットが7割引で買え、これはありがたい。BARACUTAはご存知の通りイギリス老舗ブランドであるが、今は日本でライセンス生産しているので日本製ということになる。ここのジャケットなんか5万円以上もするので正規の値段では俺の小遣いでまず無理やが7割引なら何とかなる。日本製となってても生地は中国製とか、そもそも日本製が無くなってしまった家電製品とか、まあ色々とあるが、当面はMADE IN JAPANにこだわって行きたいなと思うてるわけです。
2010.12.20
■もっと勇気を
前にも書いたが、俺は電車に乗っているとき他人のヘッドフォンなどの音モレに異常に反応してしまう。最近はアイポッドで聴いている人が多いが、音モレするのはいっしょである。特に休日の昼間などに用事があって電車に乗るとき、座って本を読めるというのが唯一の楽しみやのに、どこからか聞こえてくる訳のわからん曲の音モレはもう最悪である。先日も俺の斜め前に座ったニイちゃんの音モレが激しかった。同じ車両のかなり離れたところからもこちらを睨んでいる人がいるが、誰かが注意するわけでもない。このニイちゃんの格好は白のベストにピンクのシャツ、いわゆる鳶ズボンというのやったか、例のダボダボのズボンで誰が見てもガテン系のニイちゃんである。こんなニイちゃんに文句言うやつはおらんやろ、と小心者は諦め、あからさまに席を移動する勇気もなく、ただ、心のなかで「うっとうしいなコイツ、一体頭の中どないなってんねやろ」と呟きながら目を合わさないようにしていた。そして、以前大阪でJRの満員電車に乗っていたときのことを思い出した。その時も俺のすぐ前で音モレをさせている大学生風がいたがやはり同じように「うっとうしいなコイツ」と思っているだけで何も言えずにいた。ところが突然、後ろからその若者の頭を小突いて、「こら、うるさいど」と言ったおっさんがいた。言われたその若者も不服そうな顔をしながらもシブシブ音量をしぼっていた。こういうのを勇気ある行動と言うねやろけど、俺には100年経ってもでけん行動やね。
2010.12.08
■年寄りの冷や水
岡本太郎氏は40台後半からスキーを初めたとどこかで知ってから、もう年をとっているので今から始めるのは遅いやろ、という考えを出来るだけ持たないようにしている。サッカーは45歳からはじめ、今でも続けているが、シュート練習で下腹に力が入りすぎ、そ径ヘルニアになって手術までしたり、試合中に捻挫をしたまま3試合も続け、その後、完治まで1年半ほどかかったりと、中高齢から始めるにはそれなりのリスクがある。それに比べると、軟式野球は大学時代に愛好会(体育会の次に同好会があってその下)に入っていたし、就職してからも職場の野球部でそれなりにプレーしていたので、まあ経験者と言えなくはない。でも、大学の野球愛好会時代の終身打率は0割9分1厘と1割にも満たないのでまあ、好きやけど、ヘタっちゅうことである。で、ここ10年以上バットもグローブも触ってなかったところへ、たまたま昨年、久しぶりに野球の試合をすることになった。心配をよそにその時はバットにボールも当たったし、フライもゴロもちゃんと捕れたので、やっぱ昔取った杵柄やねと自画自賛していた。そして今年は3チームの対抗戦に拡大し、張り切って打席に立った第2打席目。当たりそこないのショートゴロに崩れた体勢からあせって走り出したとき、右足の付根にボコンとへこんだような衝撃が走り、同時に痛みも走った。そこでやめときゃええのに、ベースボールプレーヤーの端くれ、必死で1塁ベースを駆け抜けたが、その時点で、もう右足が動かず、あえなくリタイア。車に乗るとき自分の右足を両手で持ち上げないといけないような状態が1ケ月以上続いた。結局、内転筋を痛めたようで、もう1年になる原因不明の手首と同時に電気治療をしてもらっている。大事に至らなかったのはよかったけど、こういうのを「年寄りの冷や水」て言うねや、と納得。昔の人の言うことはよう聴かんとあかんね。
2010.11.29
■職業柄
義理の妹に初めて会ったころ、当時本人が看護師の現役であったということもあり、「お兄さん、血の採り易そうな血管ですね」と言われたのを今でも憶えている。背が高いですね、とか大きい足ですね、とか言われることはよくあるが、いきなり、血が採り易そうですね、と言われたのは初めてで、こういう視点ははやり職業柄かさもなければ吸血鬼くらいやと思う。以来、最近でこそ少なくなったが、「ええ血管してはりますね」と言われた事は2度や3度ではない。「血管の太い人は長生きするんですよ」とそのメリットまで説明して頂いたこともあったし、「う~ん、何ぼ見てもエエ血管やねえ」と骨董品を見る鑑定士のようにマジマジと見られることもあった。何をもってイイ血管というのかは確認したことは無いが、たぶん、太くて表皮に近いということではないかなと思う。今は、痛風の薬を飲んでいるため、献血の出来ない身体になってしまったが、献血を定期的にしている頃は、人の後から血を採り始めて先に終わるということもあったので、血圧が高いとかいうことではなくて、血管が太いために早く終わる、ということもあるのかなと勝手に思っている。まあ、職業柄っちゅうのも色々あっておもろいね。
2010.11.24
■世界の車窓より(コートダジュール)
世界の車窓より第1弾、第2弾とも電車内の写真で車窓になってないことに気がつきましたが(今頃遅い)、今度こそは窓越しに撮った風景です。ニースを出た電車の車窓から沿線をしばらく眺めていると、急に海に面して視界が開けた。目に飛びこんできたのは、紺碧の海に浮かぶクルーザーやでっかい客船。小さな湾のようになっていることころで、たぶん有名な場所なんやろけど、まったく分からない。途中いくつかの駅に停車し、けっして大きくはないが上品そうなホテルや別荘の佇まいを見ていると、俺が知らない(だけで本当はよく知られているに違いない)こういうこところが本当のリゾートなんやろなと思えてきた。よう考えたら(考えんでも分かるねんけど)このあたり一帯をコートダジュールというのやと思い出し、世界でも超一級のリゾートなんやからかっこエエのは当たり前やなと納得するのと同時に、コートダジュールなんかはたぶん行くことはないやろと思っていたので、一瞬通過しただけでも嬉しかった。何せコートダジュールと言えば、滋賀県大津市界隈では、カラオケかファッションホテルのことである。いつも「この名前何とかならんかな」と思っていたのが余計恥ずかしく思えるようになった。まあ、日仏の国際問題にまでは発展せえへんやろけど、中国のバッタもん笑うてられんな、と思えてきた。けど、よう考えたら、このコーナーもバッタもんやった。
(モナコシリーズひとまず終わり)
2010.11.17
■世界の車窓より(ニース)
バッタもんシリーズ第2弾は間がだいぶ開きました。もともと電車が特別好きなわけでもないし、海外で電車に乗ることも少ないけど、今回のネタは1流です。しかし中味が伴わないと最初から言うときます。と言う事で、モナコGP観戦の宿がニースであったことはすでに報告済みですが、ニースからモナコまでは電車で20分程度と結構近い。ホテルも駅前であったので歩いて行ける。そして切符を買おうと思ったが、買い方が分からない。Nice Riquier という駅員のいないニースでもマイナーな方の小さな駅で、自動販売機のスタンドみたいなのが立っている。フランス語しか書いてないし、現金は使えない。旅なれたメンバーがあれこれボタンを触ってみて、たぶんこれちゃうか、とうことでモナコ往復と思われるボタンを押して、クレジットカードを入れるとちゃんと切符が出てきた。電車もどれに乗っていいかわからないが、ホームが一つしかないし、方角はわかっているので来た電車に乗り込んだ。結構空いていて、子供のようにあちこち席を移りながら車窓の風景を楽しんでいた。そして乗ってしばらくして小心者の俺はこの電車でホンマにモナコに行けるねんやろか、と不安になったが、車両の中を見渡して一瞬で安心した。同じ車両の後方に陣取っている地元の人々と思われるグループは誰が見てもF-1観戦とわかる格好をしている。おそらく世界共通のF-1ファションで、お気に入りのチームのシャツと帽子を被り、そして贔屓のチームの旗を担いでワイワイ騒いでいる。こういう分かりやすいファッションはエエねえ。
2010.11.10
■欧州クルマ事情(限定情報4)
少し前に、トヨタの小型車IQのCMで縦列駐車をしているクルマとクルマの間に歩道に対して直角にクルマを駐車してテーブルを広げるのがあったが、ローマの街中では、このCMみたいに、歩道に対して縦に(直角に)駐車している車が結構多い。そのほとんどの場合はスマートであるが、それ以外でも小型車なら平気で縦に置いている。狭い街中ではその方がスペース的には合理的といえばそうかもしれんが、普段から路上駐車が多くてただでさえ歩きにくい車道の脇がさらにデコボコしている。特にトランクのある車が縦に駐車すると、歩道上にトランク部分が張り出すので、歩道を真っ直ぐ歩けなくなる。まあ、それはそれとして、イタリアといえば小型車と昔からイメージがあったが、洗練された雰囲気の女性がマイクロカーに乗ってローマの市街地を流している姿は確かにカッコいい。一方で、日本では景気もイマイチやし道路事情も大して改善されてない割りに、どうも少し前からハマーを代表とするデカいアメ車が一部で流行っているようである。滋賀の田舎町でも結構走っていて、狭い道で対向するとこっちが避けるしかない。スーパーマーケットの駐車場でも2台分占領している。人の趣味といえばそれまでの事で、エコ意識云々は別にして、まあ勝手にしなはれ、ちゅうことやけどちょっとは世間の迷惑考えてほしいね。
2010.10.31
■欧州クルマ事情(限定情報3)
乗りかかった船でもう一回だけ三本和彦氏関連でいきます。氏のクルマへのこだわりが垣間見られたのは、今はもうやってないと思うけど、たまたま滋賀でもネットしていたローカル局で見られた三本氏の長寿番組「新車情報」である。愛読誌NAVIとともに欠かさず見ていた時代があった。三本氏のこだわりには大いに共感出来る事が多く、誰も聞いてないと思うが俺にもクルマ選びに関してはいくつかのこだわりがある。三本氏のこだわりは数多くあったと思うが、憶えているのは、「ディーゼルエンジンの優位性」「三角窓の効能」「トランクの広さ」「Aピラーの角度」「頭上高は幅の3倍有効」「サッシュレスドアの不要性」「必要以上に扁平率の高いタイアの不要性」「ボディー一体型バンパーの無駄」「シンプルでしっかりしたシート」などで、現在まで何十年にも亘ってほとんどの国産車が対応していない、というか最初から対応する気のないモノが多い。流石に三角窓はもう一部の旧車しかないだろうし、乗用車のディーゼルは実質的に選択肢が無いが、その他の項目は今でも俺は車選びの基準にしている。まあ、俺の場合経済的な理由も含め、いつも欧州車の中古を買っているのは、上記のような項目が最初からクリアーされている車が多いからである。色々オンボロ車を乗り継いだが、三本氏が番組の中で「値段以外に難くせのつけようがない」と言ったアウディ80クワトロは友人から30万円で譲り受けたあと、14万キロくらいまで走ったところで天井の内張りがはがれ垂れ下がってきた。張り替えると10万円近く要るというので、ボンドでくっつけながらも乗っていたが、さすがに天井の中味までボロボロ落ちてきたので諦めた。ここまで愛着を持てる車はやっぱり北欧も含めた欧州車やと俺は思うね。
2010.10.23
■欧州クルマ事情(限定情報2)
三本和彦氏のことを前回書いてしまったので、ネタを続けます。三本氏がボディー一体型バンパーを良しとしないのは、バンパーというものはしょっちゅう当てたり、擦ったりするもので、ひと擦り何万円もすることがおかしいと。だからボディーと一体にするためのデザインやボディー同色の塗装も不要で、樹脂のままで安価に取り替えられるようにすべし、という主張。これは合理的でモットもな意見やと俺は思うが、現代のクルマのデザインや空力等を考えたら、まず無理な話であることも一応は理解する。で、バンパーで思い出すのが、「ヨーロッパでは前後を詰めて路上駐車をするため、出る時はバンパーで押して出る」という都市伝説。中学校から自動車雑誌を読んでいた俺は幾度と無くこの話を読んだ記憶があるが、大人になるにつれ忘れていたものを、今回、初めて欧州の地上に降り立ったニースの街中で思い出した。空港からホテルまでの道路わきの路上駐車の車はその停めている前後の間隔が半端でなく狭い。大きな都市の真ん中でもなく、道路に余裕が無いわけでもないのに、何でそんなに詰めるの、というくらい接近して駐車している。他のメンバーがホテルまで急いでいるなか、俺は一人立ち止まって写真を撮り、これ、誰かクルマ出してくれへんかな、としばらく待っていたが、もう日も暮れて人通りもなく、おそらく翌朝しか動かすところは見られないと判断し諦めたが、やっぱり車を出すこところを見たかった。写真からするとどう考えてもそのままでは動けないので、バンパーで前後を押して出るというのはひょっとしてホンマかもしれんと思えてきた。
2010.10.16
■欧州クルマ事情(限定情報)
ローマの街中ではドイツの車が多いのが意外やった。タクシーはベンツが多いし、自家用ではアウディやBMWが結構多い。空港からの行き帰りのタクシーは幸運にも両方ベンツのタクシーで、行きは前回書いた通りCクラスのワゴンで高速を時速160kmで巡航していた。帰りはCクラスのセダンで運転手は仕立てのいいイタリア製のスーツ(おそらく)をビシッと着ており、ベンツの後部座席に座っているとなかなかイイ気分である。欧州では高速での移動が多いちゅう事は自動車雑誌で子供の頃から嫌ほど読んでいるが、高速巡航を実感してみて初めて意味がわかった。さらにこれも自動車雑誌で読んでいた通り、ディーゼル車が多い。行きのベンツCクラスワゴンも日本には入っていない新世代ディーゼルCDIエンジンで、さらにミッションであるから凄い加速である。クリーンディーゼルとミッションの組み合わせは昔愛読していた自動車雑誌NAVI風に言えば、乗っている人の「アタマが良く見える」選択であるが、日本のマーケットではまず見向きもされないパターンである。日本の乗用車ユーザーにはディーゼル嫌いが多いため、日本の自動車メーカーもほとんど本気で開発してこなかった。自動車評論家(本職は写真家)の三本和彦氏などはしつこくディーゼルエンジンの優位性を説いていたが評論家でも少数派であり、いかんせんユーザーの理解とメーカーのポリシーがないこの国では土台無理な話しである。元々定評のあるメルセデスのディーゼルエンジンはこの間も進化を続け今の新世代クリーンディーゼルが評価を受けているのは街じゅうを走っているベンツのCDIの多さを見ればわかる。ベンツも意地をみせてかどうか、このCDIエンジン搭載の車種を日本にも入れてはいるが、Eクラスやと価格は800万円超である。俺が買えるようになるのは20年中古くらいやろけど、その頃、クルマはあっても俺がこの世にいんかもしれん。
2010.10.10
■ローマは一日にして成らず
名前の通りイージーな航空会社だったが何とかローマの空港には到着した。深夜の時間帯なのでタクシーがあるかどうか心配したが、これも何とかまだ走っているようやった。ホテルには連絡が付いているので安心やが、あるとはいえタクシーはたまにしかこない。おそらく同じ飛行機から降りた客が前に数人並んでいたので、乗り込むタクシーを観察していると、名前を知らないフィアットの大衆車かベンツかで、その差があまりにも大きい。京都駅前タクシー乗り場で順番待ちをしていて、「ああ、小型車やったらエエのになあ」と思っていると必ず中型車が来るのといっしょで、「ベンツやったらエエのになあ」と思っているとフィアットが来た。「やっぱりそうか」とがっかりして車に乗り込もうとすると、運転手が後ろの車に乗れと手振りで示す。どうもトランクに俺たちのラゲージが入らないみたいで、後ろに来たベンツのワゴンのタクシーになった。大きなラゲージを持っていて初めて得した気分になった。欧州は初めてだが、以前から車雑誌で読んでいたように、ミッションの車が多いのとディーゼル車が多いのは変わっていないようや。俺たちの乗ったベンツのタクシーもCクラスワゴンで6速ミッションでディーゼルというエコで合理的でシブいという理想の一台であるが、日本ではまず100年経っても輸入されない車種である。もちろんどこをどう走っているのかさっぱりわからないが、高速かなんかを160kmでぶっ飛ばしてローマの市内に入ると景色は一変。オレンジ色の街頭に浮かびあがる歴史的建造物だらけの町並みは古代ローマ時代にそのままタイムスリップしたような不思議で荘厳な雰囲気である。大きな建物の前を通るたびに「おお」と感激していると、ドライバーが何か解説をしてくれている。「ふん、ふん」と適当にうなずいているが何を言ってるのかもちろんわからない。近年、日本人観光客の間でもローマは人気都市となっているようやが、町並みをタクシーで走っているだけでその理由は十分わかる。使い古された言葉であるが「ローマは一日にして成らず」は一見しただけでわかるというこの歴史の深さはやはり大したもんやねえ。
2010.09.28
■名は体を表す(2)
約2時間遅れで出発した飛行機の機内では、しばらくすると先ほどの引換券とスナック・ジュースの引き換えが始まった。結構いいかげんな運行をする割に、引換券との引き換えはえらいきっちりしているようや。そもそもこの飛行機に乗っている人は全員予定より遅れている人ばっかりやし、全く大したことない中味なんやから、全員にさっさと配ってしまえばエエのにと思うが、何故かきっちりと引換券と引き換えしている。そんな段取りの悪いことをしているので半分も配り終えないうちに日付が変わる時間になってしまった。そして、ギリギリで俺のところまで来たCAが引換券を出せと言う。俺の引換券は鞄に入れてしまっていて、上の荷物入れにあるため、上に入れていると指を差した。それならいい、とすぐ飲み物等をくれると思ったら、鞄から出せと言う。「え~、ホンマかいな」とどうせ日本語は分からないだろうからと独りでボヤキながら引換券を出した。それで貰ったものは小さな箱菓子みたいなものひとつとパックジュース1個。こんなモンのためにカウンターで引換券まで配って、また回収してんのかいな、とその考え方には全く理解が出来なかった。しかも、俺のすぐ後ろで、日付が変わって引き換え時間が終わったのか、運行の都合上なのか、よう分からんが、とにかくCAたちは交換途中でさっさと引き上げてしまった。飛行機が2時間遅れようとも、中途半端なサービスがあろうとも、文句一つ言わない(ように見える)欧州の人たちは何と言うか大人といえば大人やろけど、これ関西人やったら、ほぼ全員「何やねんこれ」てツッこむと思うね。
2010.09.22
■名は体を表す
今回のモナコは何せほぼ弾丸なので、決勝が終わればローマに移動である。せっかくなので夕食はモナコで食べたが、ゆっくりくつろぐ暇も無く電車に飛び乗り、ニースのホテルに戻って大急ぎで帰り支度をし、空港まで早足で急いだ。ニースからローマへの移動は、LCCつまり安売り航空会社で、一抹の不安があったがこれが見事に的中し、デッキから眺めるとどうも飛行機が到着していない。1時間ほど経ってもどうも到着する気配もないので、旅慣れた賢明なメンバーの一人が「今日は、ニース泊になるかもわからんので、ホテルに確認してくるわ」と言って電話を掛けに行った。しばらくして戻ってくると「駅前のホテルは泊まれるので、場合によってはまた電話すると言うといた」とのことで、最悪の事態にも備えが出来、ちょっと安心した。そうこうしているうちに俺はロビーのソファで寝てしまい、1時間ほど経って目を覚ました時、周りには誰も居ないのであせった。昔、高速道路のサービスエリアで放っておかれた事があるので、まさか、と思ったが、結局、他のメンバーも暇をもてあましてあちこちに行っていただけのことであった。そうして、もう今日はニース泊か、と諦めかけたとき、やっと出発の気配が出てきた。何やら、アナウンスがあったが俺には中味は全くわからない、しかし、アナウンスの直後、乗客がカウンターに人だかりになっている。とにかく確認してくるわ、と一人がカウンターに行き、何やらチケットをもらって来た。どうも飲み物とスナックの引換券らしいが、使用期限が今日中となっている。時計を見るとあと1時間もない。もちろん売店もすべて閉まっているのにどうして使うねん、と疑問だらけである。この安売り航空会社はイージージェットというのやが、名前が名前だけに考え方もイージーやな、とこんなんシャレにもならんわと、皆文句たらたらである。(次回に続く)
2010.09.17
■モナコGPレポート(7)
レースのスタート前、スタンドの最前列に移動した俺たちは、当然、スタート直後に注目する。何せ一番波乱が起こる可能性が高いスタート直後の第一コーナーである。そして緊張のスタートが切られ、各車はスムーズに第一コーナーを抜けて行った。ちょっと拍子抜けやったが、大きなアクシデント無しにレースが始まったのはそれはそれでエエことや。で、海外のGPで何が困るかって言うと、レース解説が全然分からないこと。シンガポールGPなら少しくらい(ホンマに少し)英語のアナウンスは分かるがまあ、モナコともなるとさっぱりわからない。双眼鏡でオーロラビジョンを見て順位の確認くらいは出来るが、それ以外はレース状況がさっぱり分からない。鈴鹿では定番のピットFMで専門家の裏解説まで聞けるが海外GPではこういう訳にはいかないし、こればっかりはどうしようもない。今回のレースで言うと、目の前でバトンがリタイアしても、何回もセーフティーカーが入っても理由が分からない。ピット戦略もピット作業もチームラジオもオーバーテイクシーンもTV観戦なら何でも至れり尽くせりだが、現地ではそういう訳には全然いかない。そんなとこまで行かんでもTVの方がよう見られるやん、ていう人は一杯いるし、そういう人はそれでエエと思う。それでも現地まで行くのは、音、光、匂い、ざわめき、はためく旗、人々の顔、活気、喧騒、五感で感じるものすべてが違うからである。モナコで長年の夢はひとつ叶ったが、まだまだ行きたいGPが一杯ある。
2010.09.10
■モナコGPレポート(6)
モナコGPに行こうと決めた時、やっぱ悩むのはどこのスタンドで見るかということ。いつもの俺たちの基準では、どこのコースであっても、まず一番バカ高いホームストレートのスタンドとスピードが落ちるヘアピンは避ける。でその後は観戦ポイントの面白さと料金との兼ね合いになる。特に今回はモナコへの移動手段が決まるまでにチケットを確保することになったため、面白さと料金に移動のしやすさを加味し、最終的に第一コーナーいわゆるサンデボーテのスタンドにした。モナコはコースが狭いことで有名やが、特にスタート直後の第一コーナーでは色んなバトルが起こる可能性が高い。しかし、スタンドに座ってみて分かったのは思ったよりもスタンドの位置が高いこと。色んな案内を見ても、スタンドの高さまでは分からないので、盲点といえば盲点やった。シンガポールの市街地コースではほとんど目線とかわらんところをすっ飛んでいったので、ちょっと残念やったが、逆にスタンドが高い分、向かいのタバコ屋コーナー側も一部見えるし、メインスタンド裏の短いストレートからラスカスに曲がっていくこところやコースサイドの豪華クルーザーもよく見えた。そしてもう一つの予想外は嬉しい誤算でスタンドの混み方。普通どこのサーキットでも決勝になれば、必ずスタンドは埋まる。しかも俺たちは前から2列目なのでその前の最前列はどう考えても埋まるやろと思うてたが、結局レースが始まってもガラ空きで誰も来る気配がない。そのおかげで最前列に移動して乗り出して見られた。これチケットが売れてないのか、太っ腹で皆あまり気にしてないのかとにかくようわからんが、どっちにしてもゆっくり見られてよかった。
2010.08.30
■モナコGPレポート(5)
モナコの街は想像していたよりも暑くなかったというか、むしろ涼しかったが、街中にはオープンのカフェやレストランがいっぱいあり、昼間からビールやワインを飲みながらレースファンが熱く盛りあがっている。何を話しているのかは分からないが、F-1レースの話をしているのだけはおおよそ分かる。そしてまず、何が他の観光地と違うかっていうと、とにかく喫煙がフリーなこと。日本でも海外でももうほとんど公共の場所はもちろんホテルやレストランまで禁煙、分煙が当たり前になっているが、ここでは禁煙という概念が無いとしか思えない。結構人ごみでも普通にくわえタバコで歩いている。F-1のスポンサーにはタバコ会社が以前は多く、それでもテレビ等でのCM禁止の関係でテレビに写るレースカーのロゴまで消してしまわなければならないヨーロッパのレースの印象が強いだけにここモナコのタバコへの寛容さはタバコ好きにとっては正に天国のようなものである。まあ、タバコ屋コーナーなんていうコーナーがあるくらいやからグランプリそのものが親タバコ派といえるのかもしれんけど、反喫煙団体の人が来たら卒倒するんちゃうか、ていうくらい俺もびっくりしたね。
2010.08.23
■モナコGPレポート(4)
モナコの街はもちろん初めてだが、ここ数年の間に俺が行ったアジア、豪州、ハワイ等の日本人定番リゾートとの決定的な違いはとにかく東洋人が少ないこと。日本の有名観光地はもちろん、ハワイ、豪州なども中国、台湾、韓国の富裕層を中心に凄まじい勢いで正に高度成長期の日本人のように団体で押し寄せているが、このモナコでは短い滞在期間とはいえほとんど東洋人には出会わなかった。日本人の若いカップルと変なカップルには何組かすれ違ったくらいで、これだけ少ないと、はやりちょっと場違いな気がする。俺の所得水準からすればもともと場違いなのは当然で、伝統と気品、ゴージャスなモナコの街に中年日本人オヤジグループが似合わんのはまあ当たり前の話しやね。ちなみに写真はモナコ自動車クラブ(ACM)の前に立つ場違いな日本人。この自動車クラブは1920年代からかの有名なモンテカルロ・ラリーやこのモナコGPを主催している伝統と格式のクラブで、写真を撮ったあと、横に警備員がいることからもわかるようにちょうど入り口の前だったので、すぐに排除されてしまった。日本のJAFに相当すクラブとよく言われるが日本の大正時代から国際レースを開催している歴史と実績とは比べるのも失礼に当たると俺は思いまっせ。まあ、ちょっと権威的なとこだけは似てるかもしれんけど。
2010.08.15
■モナコGPレポート(3)
モナコの街にはさすがに高級車が多い。俺も以前ほどはクルマに詳しくないので正確なモデル名がわからないが、とにかくフェラーリ、ランボルギーニ、マセラッティはもちろん見たこともない高級車やスポーツカーが街中に路駐している。ベンツ、BMW、アウディなどは言うに及ばずで、当時日本ではまだ予約しかとってないベンツのSLS・AMGも走り回っていた。日本での価格は2400万円強だったと思うので、ほぼ走るマンションであるが、最近俺が一番気に入っているベンツでもある。(勝手に気に入っとけっちゅうハナシですが)そして、モナコのフェラーリの特徴は車体色であると気がついた。何せ、イメージカラーであるフェラーリレッドはほとんど見かけなくて、黒やシルバーが圧倒的に多い。赤いフェラーリなど定番過ぎておもろない、っちゅうことなのかようわからんが、とにかく大阪や京都の街中を「どや」みたいな得意顔でこれ見よがしに走っている赤いフェラーリなどとはだいぶ違うことだけは間違いない。街中フェラーリ比率はおそらく世界一であろうと思われるし、日本の大衆車がこれほど少ない外国も珍しいと思う。世界的不況なんざどこの国のハナシや、みたいなとこがここには確かにあって、「節約」とか「もったいない」なんていう言葉はこの国には存在せえへんのちゃうか、て思えてしまうね。
2010.08.09
■モナコGPレポート(2)
モナコの街はテレビで見てイメージしていたよりもこぢんまりとして尚かつ傾斜地であった。レース前にはコースを一周しようと思っていたが、有料の各観戦スタンド付近は予想以上に厳重に立入り禁止になっているため、思ったようにコース見学は出来なかった。傾斜地には小さな家や店がへばりつくように密集している坂の間を縫うように狭い小道がいっぱいあり、行き交うレース観戦客で賑わっている。そのうちのひとつの坂にさしかかったとき、階段に行儀よく一列に並んでいる集団があった。決して広くない階段のほとんどを占拠しその人たちは身動きせずに座っている。最初は何をしているのかさっぱり分らなかったが、全員が同じ方向を見ているため、視線を同じ高さにしてその先を見て納得した。少し高台にあるその階段に座って海側を見ると、ほんの少しだけF-1のレースコースが見えるのである。これではレースカーの通過時間も一瞬やろし、見える距離もわずか、それに何よりコースからかなり離れているため音もどれだけ聞こえるかわからない。しかし、それでもタダ席には違いない。レース1時間以上前からきゅうきゅうにつめて座っているその姿は何か豪華なモナコGPにそぐわないようにも思えたが、やはり世界中どこへ行ってもこういうレースファンはいるもんやと安心もした。俺も20年前には鈴鹿でタダ席をとるため徹夜でゲート前で寝たこともあるがもうそんな事も出来ない。でも、とにかくレース場に出かけ、その雰囲気を味わうだけならいくらでも方法はある。豪華クルーザーのデッキに寝そべり、シャンパンを飲みながらレース観戦する超セレブからタダ席で一瞬の雰囲気を味わう若者までそのすべてがF-1グランプリであり、伝統のモナコである。やっぱF-1の中でもモナコは特別やと言われるのがちょっとだけ分かったような気になった。
2010.07.30
■モナコGPレポート(1)
ぐだぐだと脱出編を続けてきましたが、最初に戻ってモナコGP本体のレポートに行きます。(もうええちゅうハナシもありますが)しかし、2ケ月以上も経っているのでどれだけ思い出せることか。まず、モナコGPといってもF-1期間はモナコのホテルはボッタくりでバカ高いため、そもそもモナコには泊まれない、というところがある。で、いくつかの案のうち最初の計画ではローマに泊って、決勝当日にローマからニースに飛んで、電車では時間的に厳しいのでヘリでモナコに入る、というカッコええプランを考えていた。鈴鹿のF-1でもバブルの頃は名古屋空港からサーキットまでヘリが臨時で就航していたが、ニースの空港から定期的にモナコまで飛んでいるっちゅうのがさすがである。しかも、片道は確か8,000円くらいで一生に一度なら乗ってもエエなと思うくらいの値段である。もし、このプランで行っていたら、空港閉鎖の心配もせず帰ってこられたんやが、結果的には、俺は、往路はエールフランスでパリ経由、帰路はKLMでアムステルダム経由にしたのである。これは往復ともビジネスクラスで行ける特典航空券をマイルの達人であるメンバーが見つけてきたからである。必要なマイルは12万マイルやが、足りない俺の手持ちマイルに買い足したりさらに人から譲ってもらったり、またなぜかボーナスマイルがラッキーにも付いたりするデルタ航空のマイレージプログラムを最大限利用し、ほとんどの人が「えっ」と言うような値段でヨーロッパ往復をビジネスクラスで行けることになった。他にも小技があるといえばあるが、まあ持つべきは情報通の友人で、値千金とはよう言うたもんやが、軽く数十万円分に値する情報ちゅうことですわ
2010.07.24
■ほぼ弾丸欧州紀行(ローマ脱出)
ゆっくり食事をとっていたため、ホテルに戻ると深夜になった。荷造りは出来ているし朝も早いし、何よりフラフラなのでもちろんすぐに寝た。これだけ疲れていれば夜中に不安で起きることはないやろうと安心して眠りにつき、あ~結構寝たなという感じで目が覚めたので、時計を見ると朝の1時半であった。え~ホンマかいな、と思ったがどうしようもない。なんぼなんでもこれではあかんと思い、何とかもう一度無理やり眠た。そして今度は朝やろと思い、目が覚めるとまだ3時半やった。どうすんね、と思ったが、そや航空会社に電話しようと思いついた。ちょうど日本のビジネスタイムなので人の迷惑にならんように部屋を出て、エレベーターホールまで行きKLMの東京事務所に電話をした。電話番号は前日調べて日本から送ってもらっていたのである。電話は一回でつながり、女性オペレーターに便名を伝えると、サービスのかけらもないような事務的な口調で、「867便は昨日はキャンセルでしたが今日は予定通りですね」と答えた。向こうにとってみたら飛行機がキャンセルなることなんかは日常茶飯事やろけど、こっちにとったら一大事である。でもまあ愛想は悪いけど話の中身はよかったのでほっとして「そうですか」と言うと、「念のため別の方法で確認しますのでしばらくお待ちください」と電話を保留にされた。実際の待ち時間よりもこの保留時間は相当長く感じていたに違いないが、俺の為に念のため調べてくれていると思うとこの無愛想で事務的なオペレーターが天使のように感じられた。そして返事はやはり今日は予定通り飛ぶとのこと。すこし落ち着いて寝られるかと思ったが、それでも寝たのか寝てないのか分からんような状態で朝を迎え、タクシーで空港に向かった。ローマの空港は日本人の客も係員も一人もいない状態で不安やったが、何事も無かったかのように手続きも進み無事アムステルダムの空港に着いた。ここでの乗換えが最後の関門と思っていたが出国もスムーズに済み、関空行のゲートに着いたときの嬉しかったこと。何が嬉しかったというて、当たり前やが、ほとんど全員が関西人で関西弁だらけ。関西のおっさんやおばはんの大群に出会ってこれだけほっとしたことは今までなかった。やっぱ関西弁はエエもんやね。(脱出編終わり)
2010.07.17
■ほぼ弾丸欧州紀行(ローマ最後の夜)
一旦ホテルに戻り、俺だけは翌朝早いため出発準備をし、夕方ホテルを再出発した。晩御飯の予約は8時半だが、ちょうど、トレビの泉の近くなので、スペイン広場、買い物、トレビの泉の順にめぐることにした。スペイン広場もトレビの泉もあまりにも有名で、スクリーンやテレビ、雑誌で嫌というほど見ているためか、思ったほどの感動は無かった。「ああ、これこれ、よく見るヤツや」ていう感じで、情報がたくさんあることが必ずしも良いとは限らんな、と思ったが、かといって各名所の謂われを知っているわけでもない。まあ、他の観光客もとにかく観光名所やから集まってきてる、ていう風に見えてしまった。買い物も特にアテがあったわけではなく、結構歩き回って疲れてきたので、ビールでも飲もうということになり適当な店を探したが、時間的に食事が必要と言われる店が多く、結局グルグル回ってまたトレビの泉の近所のバーに戻り休憩した。ビールを飲みながらウダウダしゃべっていると時間は早く立つもので、レストランの予約時間になった。この日行ったレストランもメンバーが日本で調べてきた最近ネットで一番人気のところで、裏路地にある小さな店なので定員も少なく、そのため8時半の予約をとるのがやっとやったみたいや。しかしまあ、さすがに人気店だけあって、味もボリュームももちろんワインも旨かった。出された料理はすべて残さず食べるのが常の俺だが、最後のデザートは食べきれなかったくらいであった。もっとも連日の睡眠不足と長時間歩き回った疲れと、何より明日の飛行機の不安が交じり合って、食事の終盤はもう目を開けているのが精一杯やった。それでもこんな状態やと、不安で寝付けん、ということだけはなさそうやと、それだけは安心していたが、実はそれが甘かったのである。(ローマ出発に続く)
2010.07.07
■ほぼ弾丸欧州紀行(ローマ観光の巻3)
家族からのメールの中味は、「スキポール空港が再開しているらしい」とのこと。心配性の俺は「スキポール空港のHPを見て、書いてある内容を変換ソフトで変換して送ってくれ」と返事した。しばらくして、再開の情報は正しい事が分かったが、当然、乗る前には空港に確認せよ、との注意書きが付いていた。俺の携帯電話は、全世界対応の中では当時一番安かった韓国LG製の安モンであるが、このときはもう命の電話状態で、この二日間はどんな日本人の若者よりも携帯依存症になっていたと思う。しかし、俺が生まれた昭和30年代からすれば、もう考えられんくらい便利な世の中で、古いローマの街並みの中で日本と携帯電話でやりとりしていると自分がSFの世界に入り込んでいるような錯覚に陥る。まあ、少しは気持ちが楽になったが、ワインショップに寄っているうちに雨脚が強くなってきた。夕食の予約は8時半になっているし、これから回る予定の観光地もちょうどホテルの反対方面であることもあり、一旦ホテルに帰って体勢を立て直すことにした。明日の出発時間も結構早いため、俺は荷造りをしておく必要がある。しかし、こうなると帰り支度もちょっと気合が入ってくるというモンである。
(もうちょっとローマは続く)
2010.06.28
■ほぼ弾丸欧州紀行(ローマ観光の巻2)
昼食はやっぱりイタリアンやろ、っちゅうことで、メンバーがあらかじめ日本で探しておいた店を目指して裏道をあっちこっち歩いたが、どこまで歩いても目指す店には行き当たらない。腹は減ってくるし、飛行機が不安やしということでフラフラになりかけているとき携帯に日本からどうでもいいような電話が架かってきた。かけてきたのは友人であるが、こいつはめったに電話をしてこないのに、不思議と俺が海外にいる時に架けてくる。そして、海外にいる時は呼び出し音が違うらしく、電話を取ると「なんや、今度は何処にいてるんや」と聞く。「ローマやローマ」と答えると、「そら、ド気楽で結構やな」といつもの調子である。「それはそやけど、空港が閉鎖で明日帰れるかどうかわからんねや」と不安を訴えると「へえ、そうか、また電話するわ」とあっさり切ってしまった。自分に関係のないことには無関心ないのがこいつの特徴である。そして、歩道の犬の糞を避けながらしばらく裏道を右往左往していたが、どうも地図を見間違ったらしい、ということが分かった。どうしようという事になったが、立ち往生したところにちょうど小さなレストランの看板が出ていたので、「もうええやん、ここにしよう」という事になり、店に入った。店は手前の右側がカウンターになっており、左側には料理が並んでいる。どうもビュッフェスタイルのようで、案内された奥のテーブル席の正面にはステージとフロアーがあり、夜はクラブになる店が昼食もしているみたいや。オフィス街の裏通りのようなところで、ちょうど昼時だったので、店内はサラリーマン風の客も多く結構混んでいた。料金は一人7ユーロとやはり地元価格というか、リーズナブルである。俺は、次の日の飛行機の事が心配で、それほど、食べ物には関心がいってなかったが、ここの料理はどれも旨かった。料理の名前も中味もわからないので、とりあえず全品少しづつ取っていったが、どれもこれも旨かった。飛び込みでもええ店やったね、とか言いながら、店を出ると、家族からメールが届いた。(ローマはさらに続く)
2010.06.21
■ほぼ弾丸欧州紀行(ローマ観光の巻)
確かにホテルで一人心配しててもしゃあないし、ローマなんかもう、今度いつ来られるかもわからんので、とりあえず市内観光に向かった。比較的海外経験が多いメンバーもローマは初心者なのでド定番の観光地めぐりをすることにした。最初はやっぱりバチカンやろっちゅうことになり地下鉄で行くことにした。切符は人に買ってもらったので、はっきり見てなかったが、そもそも何線で何処まで買っていいのかもわからない俺にはとても買えそうな感じではなかった。で、地下鉄最寄り駅オッタヴィアーノ駅から外に出ると、雨。しかも平日にもかかわらずサンピエトロ大聖堂は大行列。それでなくても乗り気でなかったので一層暗い気分になった。それでも、列に並ぶと比較的流れはスムーズで意外と早く入れた。しかし一歩中に入ると、もうその存在感というか、雰囲気に圧倒されてしまった。とにかく凄いということは分かるが、何が凄いかは言い表せないのが情けない。F-1の凄さは表現できてもバチカン宮殿の凄さは全く表現できない。そもそも知識が全然足りないので、まさに「猫に小判」「豚に真珠」状態である。トムハンクスの「天使と悪魔」を見てなかったら、おそらく中学校の教科書の写真くらいしかイメージがないので、何しろ何を見ても「これは凄いなあ」としか言いようがない。世界中には行きたくても行けない敬虔なカトリック教徒がたくさんいるやろうに、と思うと何か申し分けないという気持ちの方が強くなってきた。それに、明日は飛行機飛ぶねんやろかという不安が常に頭の片隅に引っかかっているため、何ともいえん複雑な気分でバチカンを後にし、昼食に向かった。
(ローマはつづく)
2010.06.14
■ほぼ弾丸欧州紀行(空港閉鎖の巻)
モナコGPの決勝後、ニースからローマへの飛行機が遅れ、ローマ市内のホテルに着いたのは前日に引き続き深夜になった。その翌朝、睡眠不足が蓄積しているところへ、友人が真剣な面持ちで部屋に入ってきた。「おい、岡川大変や、空港が閉鎖や」。一瞬にしてその理由もわかったが、信じたくないという気持ちが働き、「え、なんで」と聞き返した。「また噴火や。スキポールが閉鎖やて今CNNで流れてる」と俺を絶望させるのに充分すぎる情報である。スキポール空港は次の日俺がローマから乗り換えるアムステルダムの空港で今回の噴火では風向きもあり、イギリスのヒースロー空港とオランダのスキポール空港だけが閉鎖になっているらしい。明日もスキポールが閉鎖になると、ローマからの飛行機も飛べず、俺はローマの空港で足止めになるしかない。俺以外のメンバーは次の日、ボローニャに移動してしまうし、さらに次の日空港が閉鎖になっていないパリ経由で帰るため、俺は完全に孤立してしまう。前回の噴火では最高6日間も足止めを食ったらしい、とか不安を増大させるような情報しかなく、本当に目の前が真っ暗になった。そして、俺以外の旅慣れているメンバーの結論は、「まあ、明日になってみんと分からんね」というごもっともな話で、「心配しててもしゃあないし、はよ観光に行こ」ということになった。俺みたいな小心者は心配で居ても立ってもいられんが、確かにホテルで一日寝ててもしょうがないので、とりあえず市内観光に出た。(さらに続く)
2010.06.04
■ほぼ弾丸欧州紀行(プロローグ)
数ヶ月以上前から今回の欧州旅行の計画は出来つつあった。旅のメインは何といってもF-1最高峰モナコGPで、中学時代から鈴鹿サーキットに通っている俺にとっては人生の3大目標のひとつである。せっかくモナコに行くんやし、という事はもちろんあったが、それでもまだ仕事が現役でもあるので、他のメンバーよりもスケジュールを一日短くし、俺だけは3泊5日の日程にした。旅行初日は朝6時に起きてからニースのホテルに入るまで24時間以上かかる。次の朝電車で午前中にモナコに入り、午後の決勝レースが終われば、その日のうちに深夜までかかってローマに移動。3日目の一日だけはローマ市内観光で、次の日の朝にはアムステルダム経由で一足先に帰るというほぼ弾丸の強行日程である。最初は2泊4日にしてレースの次の日に帰ってこようかと思ったくらいであるが、何ぼなんでもということでこの日程にした。しかし、この日程とコースが後になって重大な分かれ目になるとは夢にも思ってなかった。後から色々考えると、念願のモナコ観戦のわりに、旅行前になっても何故か気持ちが盛り上がらなかったのが自分でも不思議で、それが何によるものかはもちろん分からなかった。そして、そのえもいわれぬ不安が的中したのは2日目の朝。神妙な面持ちで俺の部屋に入ってきた友人の言葉に目の前が真っ暗になった。(続く)
2010.05.24
■淡路サイクリング(テンぱる店主)
本格組とシロート組ではスピードも距離も違うが、昼は全員同じところで食べようということになり、旨いと評判の寿司屋で集合することにした。岩屋から出発した両組は途中で分かれ、本格組は慶野松原を折り返して帰ってきて寿司屋でシロート組と合流である。シロート組はそれなりに坂道を登ったりしながらも名物のソフトクリームを食ったりして余裕で先に寿司屋に到着した。途中、電話で18名の予約を入れようとすると、「そんな大勢の予約は出来ない」と言われ、早めに着いて席を確保しようという考えもあった。そして先着の8名だけでも先に、と店に交渉に行くと、まったく受けられないという。もうすぐ予約が入っているとのことで、待ってもらっても困る、みたいな顔をされたらしい。カウンターは空いていたらしいが、とにかく店の許容能力をはるかに超えているみたいで店主も店員もほとんど対応する気なし、のような状態やったらしい。これではいくら旨い店でもあかんな、ということになり別の店をあたった。少し遅れて本格派がこの店に着いたとき、店は準備中の看板に変わっていたらしい。もう完全に商売やる気なしやね。でもネット情報を元に次にあたった店は、大将の愛想もよく、席もいくらでも準備してくれたし、寿司も旨かった。しかし、それですべてが上手くいくほど世の中は甘くなく、大将が一人で寿司を握っているため、全員が食べ終わるのに滅茶苦茶時間がかかった。まあ、皆さん書入れ時やから、異様に張り切ったり、テンぱったりするのも分からんでもないけど、そう思うと連休の分散化っちゅうのは必要かもしれんね。
2010.05.15
■淡路サイクリング
昨年に続き、大型連休中に淡路島にサイクリングに行ってきた。今年は本格派9名とシロート5名、車でのサポート1台3名、バイク1台1名の合計18名の大部隊であった。シロートと本格派は平均スピードが倍ほど違うので、当然目的地も違い、走行距離もそれぞれ、約50kmと100kmと倍である。淡路島サイクリングの(最大の)楽しみは食べ物で、焼き穴子、天ぷら、寿司、ソフトクリーム、それから明石に戻ってからの卵焼き(明石焼き)は毎年の定番コースで、消費したカロリーよりも摂ったカロリーの方が多いんちゃうか、というくらい食べものが旨い。本題のサイクリングは海沿いの道がほとんどなので景色は抜群であるが、景色をのんびり眺めながらというわけには中々いかない。道幅が決して広くない一般道なので、自転車のすぐ脇を走っていく車に結構気を遣いながらの走行になるし、特に大型車が通過するときは風圧で吸い込まれそうになる。さらに、道端には迷惑駐車の車があったり、地元のオバサンがママチャリで逆走してきたりと気を抜けない。今回も、メンバーの一人が畑に転落、あわや大事故となるところだったが、もちろんヘルメットを被っていたおかげもあって、顔と膝の軽症で済んだというきわどいアクシデントもあった。自転車ブームと高速1000円効果の両方で淡路島も自転車と車が相当増えている感じがする。赤字タレ流しの空港いくつも造ってるくらいなら、全国にサイクリングロード整備した方がよっぽどエエのにといつも思うわけですわ。
2010.05.08
■40年目の真実
大人になっても昔の憶え間違いが正しいと思っていて恥をかくことがある。ことわざの憶え間違いや解釈違いなどが代表で俺も40年ぶりにわかった事があった。学生時代に英語のことわざを習った記憶は誰にでもあると思うが、対応する日本語のことわざを先に知っていることの方が圧倒的に多いので、結構違和感を感じることがある。例えば日本語の「覆水盆に返らず」を俺は「覆水盆に戻らず」と間違って憶えていたのだが、これがさらに英語では「It is no use crying over spilt milk」で、水でなく牛乳になるので、やはり変な感じがする。そしてホンマに最近気がついた勘違いことわざは日本語の「早起きは三文の徳」でこれは英語で「The early bird catches the worm」になる。俺は約40年間この最後の部分を「warm」と思っていた。早く起きれば人よりも早く暖かい日差しが浴びられるから、というのが俺の勝手な解釈で、欧米人にとって日光浴は贅沢なことと聞いていたので、鳥もいっしょなんか、さすが欧米やな、とホンマに思っていたのである。ちょっと考えたら鳥が日光浴するはずは無いねんけど、「ウオーム」という発音からは「warm」 しか思いつかなかったのである。そういやブラックバス釣りが流行ったとき餌に「ワーム」というのがあったし、それは虫の擬似餌やったけど、俺の頭の中では結びつかへんかった。英語塾の教科書であらためてことわざの文書を見て「あれ?」と一瞬読むのを停めてしまった。まあ、自分だけにしか分からんことなんやけど、絶対人に言うてしまいそうやな。
(もう言うてるっちゅうねん)
2010.04.30
■合鍵
俺はよくお世話になる合鍵であるが、ついこないだは家族が遠方で車の鍵を紛失し、家にある予備のキーを送って何とか事なきを得た。車なんかキーが無かったらただの金属の粗大ゴミでどうしようもない。で今回は、ガレージの予備キーが無いことに気づいて、合鍵を作りに行った。最初に行ったのは大手日曜大工センターで、「この鍵のスペアー作って欲しいんですけど」と見せると、若い女性店員は「う~ん」と困ったように唸って、「この鍵は取り寄せになります」とか「今日は技術者が居ないので明日になります」とか「私はまだ見習いなのでよく分からない」とか言いだした。「じゃあ、また来ます」と言ってすぐに店を出た。困ったなあ、明日まで待ってられんしな、と考えながら車まで歩いている途中で、地元の金物屋さんで合鍵を作ってくれるという話を思いだした。金物屋さんに行くと、結構広い店内で中年の女性が一人で留守番をしていた。「このキーなんですけど」と見せると、「う~ん、あったかなあ」とまた不安な事を言いながら、スペアキーの元が一杯並んでいる棚のところに行って見ている。そして「これかなあ」とか言いながら、スペアキーの棚の裏側に行ってしまった。何してんねんやろ、と思っていると、「ウィーイン」という機械音が聞こえてきた。あれ、もう加工してるやん、と思っていると、もう一回「ウィーイン」と音がしてしばらくすると、「出来ました」と言って、頼んだ2種類の合鍵が数分で出来上がってきた。値段は1個税込315円。合鍵を作るっちゅうことは商売屋さんなら簡単なことなのかどうか俺にはわからんが、けど、これ合鍵が無かったら車も、ガレージも家も何にも使えへんちゅう意味でホンマに凄いといつも思う。これ使用価値から言うたら、300円やそこらやなしに3,000円くらい取ってもええと思う。それくらいにしたらちょっとは皆、鍵の保管に気をつけると思うで。(俺の事か)
2010.04.26
■タイヤ選び
例年3月になると冬用タイヤを夏用に替えるんやが、年末に痛めた手首がなかなか回復せず交換作業が億劫なため、4月に入ってもまだ冬タイヤのままである。それにしてもボチボチと思い、車庫のタイヤを見て、今年6月の車検までに新しいのに買い替えなあかんのを思い出した。デフレの影響もあり、各店舗の安売りチラシも毎週入っているため、とりあえず見に行くことにした。まず、自動車部品販売大手のA社に行った。ここは俺が好きなイタリアブランドPのタイヤを安売りしている。特価タイヤが積まれている場所には明らかに店員と分かる若者が2人いるのが遠くからも確認できたので、説明はすぐ聞けるな、と思った。タイヤ交換はタイヤ代以外に入れ換え工賃とか、バランス料とか古タイヤ処分料とか色々と別途料金がかかることがほとんどのため、すべての料金込みで比較する必要がある。それと、俺の車は古い輸入車のため、最近の国産車ではほとんど見られないサイズが標準のため、互換サイズも聞きたかったのである。タイヤの前で、ひとりブツブツといかにも悩んでいるという雰囲気を出して立っていたが、店員の二人は全く様子を伺いにくる気配もみせず雑談を続けている。わざと別のタイヤコーナーも一周して店員のすぐ前のタイヤの前に戻ってきたが、それでも反応がない。もう一軒の方を先に回ろ、と思いそこから2~3分のところにある国産タイヤメーカー系の販売店に行った。車を降りて、店外に展示しているアメリカブランドFの特価タイヤを見ようと近づいていくと、背後からすっと寄ってきて「サイズを確認いたしましょうか」と店の人から声がかかった。タイヤ専門店なので当たり前といえばそれまでやが、疑問にもテキパキと答えが返ってくるし、詳しくは店内でということで俺のサイズを取り寄せてくれることになり即決した。価格の比較を細かくしたわけではないが、こうなると多少の価格差は問題でなくなる。人がモノを買うのは値段だけではない、ちゅうことはちょっと考えたら分かることなんやけどねえ。
2010.04.17
■お誂えシャツ
学生時代から百貨店が好きで、学校帰りにはよく百貨店に寄って行って色んなコーナーを買いもしないのにうろうろしていたが、お誂えシャツのコーナーだけは全く関係がないと思っていた。バブルの時代が去って久しいし、最近はさらに百貨店の売り上げも厳しいらしい。だいたい自分で考えてみてもここ何年間も百貨店で食料品以外を買ったことがない。そんな状況の中で、ハナから俺には関係ないと思っていたお誂えシャツの券をたまたま頂いた時は「ああ、そういやこういうモンが世の中にはあったんや」と懐かしさとともに軽い感動を覚えた。近年仕事ではユニクロのシャツしか着てないし、これからは鎌倉シャツにちょっと凝ってみようかと思っているがそれでも数千円の話である。シャツのお誂えとなると、仕立て代が入っているとはいえ、最低でも1万5千円はするシャツである。どんなにエエんやろと楽しみに百貨店のお誂えコーナーに向かった。平日の夕方であるからか、あるいはそれにもかかわらずなのかよく分からないが、売り場は閑散としていて、店員同士で立ち話をしているのが目立つ。お誂えシャツのコーナーに行っても、一人しかいない担当者が不在で、先客らしい2人連れが座っていた。しばらくして戻ってきた担当者らしき男性に用件を告げると、しばらくお待ちくださいとイスをすすめてくれたのはエエが、女性2人連れの先客と同じテーブルに並ぶようにイスを置かれた。おそらく接客コーナーが1つしか無いねんやろけど、こんな相席は相手も嫌やろと思い、一瞬だけ座ったが、すぐに生地の見本を見るような格好をして席を立った。しばらくして俺の番になり、さすがに何箇所も採寸をされ、こんだけ測ったらエエもん出来るやろな、とちょっと楽しみになったが、仕上がり日を聞いて愕然とした。何と注文日から27日後であるから約1ケ月後。12月にベトナムに行ったとき、一緒に行ったメンバーのうち何人かは生地とシャツの見本を持ち込んでいた。シャツを縫ってくれる店があり、生地と見本を持ち込んでおくと、翌日の夕方に出来上がるのである。まあ、比べること自体に無理があるのかもしれんけど、20倍も30倍も仕立てがエエとは思えんねけどね。
2010.04.09
■ビニ本屋
懐かしい響きやね、ビニ本。ある一定の年齢以上の人でないと、この何ともいえん恥ずかしいような、嬉しいような響きは伝わらんと思うが、何か時代の徒花っちゅう感じが俺はするね。で、何でビニ本を思い出したかというと現代にもあったからである。確かに、コンビニでも奥の方の一部コーナーにビニールがかかっている雑誌を置いているところが今でもあることはある。これ、買っている人を俺は見たことがないが、これは正しいビニ本の売り方ではないと俺は思う。でまあそれはええとして、今回俺が、たまたま入った大手コンビニチェーン店は何と、店内の雑誌にほぼすべて(99%くらいかな)ビニールがかかっていた。俺は、週刊誌は「週刊現代」と「週刊ポスト」のどちらにしようかいつも迷うのやが、パラパラめくって読む記事の多そうな方を買うのが通例で、今回も車で走っていて、週刊誌を買うために入ったのであるがこれではどうしようもない。こんな、一般週刊誌にまでビニールをかけるっちゅうのはよほどの事やろうとは思うが、俺は、そのビニールかけの作業を誰がしてるのかが気になった。最初からそういう仕様があるねんやろか、とか、バイトの学生が仕事としてやってんのやろか、とかレジで聞いたらよかったな、と後で後悔するくらい気になった。けどまあ、普通一番気になるのはその理由の方で、店長の趣味とかそういうのでは無いと考えるべきで、そうすると切羽詰ってのこととしか思えへん。それも俺が思いつくのは近所に有名マンモス大学があるっちゅうこと。俺があまり言いたくないここの大学生の立ち読み対策やとするとこれはちょっと悲しい話やね。レジで聞くねんやったらこっちの理由の方が先やね。
2010.03.30
■黄砂に吹かれて
何か、そんな唄があったなと思うが、それにしても、こないだの日曜日の黄砂はひどかったね。京都に行く用事があったので、車で走ってたら、紺色の車があっという間に泥だらけ、というか砂だらけになってしまった。京都の市内を走っている車も皆、砂まみれで特に黒いタクシーなどはかわいそうなくらいやった。なんでこんなに遠くまで飛んでくるのか不思議やけど、どっちにしても迷惑な話やね。これ、偏西風に乗ってくるのかと思うが、たまには風が東に吹かんかな、と思うね。花粉にしても黄砂にしても昔はこんなになかったと思うが、症状が出る人には深刻な悩みやと思う。俺は今のところ大丈夫やけど、年をとってから黄砂のアレルギーが出た知り合いもいるし、いつ出るかわからんな、と思っている。で、こうなると、車に戻って考えることは皆いっしょで、何年も車を洗っていない俺でもさすがに洗車機にかけようと思ってしまう。そしてスタンドに行くと、洗車機は長蛇の列。もう一軒のスタンドも外の道路まで列を作っている。昔はやった洗車場にこれも何年かぶりに行くとこちらも一杯。最近は50円洗車とか100円洗車があり、そら誰も手で洗わんわな、と思うが、待つのも嫌なんで、ホンマに数年ぶりかで車を手で洗った。そしてこうなるとこれも都市伝説やないけど、車を洗った翌日は大雨。俺が手で洗うより綺麗に黄砂を洗い流してくれた。やっぱ天気予報はちゃんと見とかんとあかんね。
2010.03.25
■王将の謎
俺が、京都に通っていた学生時代からあった餃子の王将が不況下でも絶好調らしい。確かに旨い、安い、早い、であるから流行らないハズはないやろし、巷間ささやかれているように企業努力も凄いと思う。オープンキッチンなんかもそのひとつで、カウンターに座って忙しく、手際よく、明るく、元気に厨房内で働いている若者を見ていると何かこう見ている方も活力が沸いてくる。電車の中やコンビニの前でへたり込んでいる若者もいっぺん王将の床掃除でもしたらどうやと言いたくなるくらいや。(もちろん言えへんけど)それにしてもいつも不思議なんが、あのひっきりなしに通る注文をどうやって聞き分けてんねやろっちゅうこと。一回注文が通るとだいたい5~6品は通ってるみたいやし、それを3人くらいが連続してマイクで通してるのがしょっちゅうで、俺なんか絶対覚えられへん。注文が通ったら自分の担当料理の皿を並べて管理してるっちゅうのは聞いたことがあるが、それでも焼きソバの木耳抜いてくれとか、何とかを大盛りとか、何かを少な目とか、イレギュラーな注文を誰も聞き返しもせず、一発で何人もの調理人が「へーい」とか返事してすぐに調理にかかっている。俺が学生時代にバイトをしていた近鉄名店街の中華料理店では注文が重なったら必ず「都合いくつ」と言っていたし、調理人は調理人で注文伝票を見ながら、あと何がいくつか確認していた。まあ、それも慣れとか、能力とかの問題かもしれんけど、流行ってる店っちゅうのは無駄な動きがないのだけは確かやね。さらに、英語を何年も習っててもABCストアーのレジのオネエちゃんの言うてることがさっぱり聞き取れへんねやから、俺の聞き取り能力が著しく劣ってるっちゅうのもあるやろね。
2010.03.16
■個人タクシー
京都には昔から結構ユニークな個人タクシーがあったと思うが、わざわざつかまえる事はむつかしい。30年以上前の学生時代にも車内を豪華に飾りつけたちょっと有名な個人タクシーがあり、走っているのを何回も見たことがあるが、結局一回も乗ることはなかった。 今回、たまたま四条高倉のタクシー乗り場から乗ったタクシーはタクシー仕様ではないホンマもんの最新型のクラウンロイアルサルーンであった。以前(相当前)は京都の個人タクシーは淡い緑色の車体が目印であったが、最近は他の色もあるようで、今回乗った個人タクシーも車体はブラックで、高級なハイヤーか役員公用車のような雰囲気でちょっと社長気分である。エンジン音も静かやし、高級感をウリにする個人タクシーはガソリン仕様が多いので、運転手さんに「これは、ガソリンですか?」と聞くと「ガソリンとLPガスと両方です」と聞きなれない返事であった。「へえ~、そうですか」と意味が分らないまま適当に答えておいたが、後で調べてみると、どうもLPガスとガソリンを併用するバイフェーエルという最新のシステムのようや。まあ、それはそれとして、車が走りかけると天井から液晶モニターが降りてきた。何やこれは、と思っていると、「1曲どうですか」とマイクを渡された。カラオケのシステムを積んでいるのである。マイクがちょっと太めでその中に曲のデータが入っているとのことで、同乗の知り合いが「何曲入ってるんですか?」と聞くと「1000曲です」という答えであった。俺は既にちょっと飲んでいたし、気分もよかったので、短い時間で2曲歌ったら、2回とも95点以上の点数が出た。もともと近い距離であったが、あっという間に着き、気分よく降りると、同乗していた同僚は、「あのさっきのカラオケの得点ね、あれ、運転手さんがハンドルの下で操作してるんですわ、きっと」と疑っていた。実際そうやったとしても客を楽しませるためやったらそれも立派なサービスっちゅうもんやね。まあ、余裕のある個人タクシーやから出来るっちゅうことはあるやろけど、こういうタクシーに当たるとちょっと得した気分になるね。
(おまけ)
この後、用事が終わり、帰りのJRの時間がギリギリになったため、川端通りを京都駅までタクシーで急いでいると、偶然前を先ほど乗った黒いクラウンのタクシーが走っていた。俺は昔駐車場でバイトしていたこともあり、車のナンバーを確認するクセがあるので、先ほどタクシーを降りたとき、「1515」というナンバーを覚えていたのである。乗っているタクシーの運転手さんに、「この前を走ってる1515の個人タクシーさっき乗ったんですわ、カラオケが出来ますねん」と言うと、「ああ、この車、祇園の周辺でよう見ますわ」との答え、さすが業界の事である。さらに信号待ちでわざわざ横に並んで、二人してそっとクラウンの運転手を覗き込んだ。そして、意外と若い運転手さんやね、と感想も一致した。この運転手さんも乗ったときの俺の雰囲気を察してかなり急いでくれたし、ちゃんと会話も成り立ったし、たまにはこういう良い運転手さんに当たる日もあるんですわ。
2010.03.11
■鎌倉シャツ
少し前から話題になっている鎌倉シャツを買ってきた。関西には店がないので、いつか機会があればと思っていたが、東京での用務中に1時間だけ時間が空いたとき、今しか無いと思い急いで行ってきた。店はネットで見て想像していたよりも小さく、また、これも予想外に女性客が多かった。男性モノのシャツは3月にたくさん入荷予定とかで、首周りが43cmとあまり一般的でない俺のサイズはほとんど無かったが、試しにと思い、セミワイドカラーのストライプを1枚だけ買った。値段は税別で4,900円と噂どおりで、120双の糸を使っているらしき表示を見ると国産でこの値段は確かに安い。ここの社長は、我々が服飾のイロハを学んだ伝説のヴァンジャケットの元社員で、この社長がこだわるシャツはユニクロの柳井会長も着ているというくらい折り紙つきのものである。東京駅前の丸の内ビル店は俺が行ったときは女性店員(ひょっとして店長かも)が一人で対応しており、数人いる客に対して同じように丁寧に説明していたかと思うと、レジを打っており、正にてきぱきと切り盛りしているという感じやった。俺がレジにシャツを持っていくと、「出張ですか?」と気さくに声を掛けてくれた。「そうなんですよ、大阪に無いからわざわざきたんですわ」と冗談交じりに言うと、「すいません、名古屋の向こうは広島で大阪が飛んでいていつも言われるんです」と言う。そして、「スタンプカードはありますか」と聞くので「持ってません」と答えると「お金はいりませんし、すぐ作れますから作っておきますね」と手早くカードを取り出し、1個スタンプを押し、さらに「さきほどのお連れ様の分も押しておきます」ともう一個押してくれた。いっしょに行きネクタイを買った連れはスタンプカードはいりませんと先ほど断っていたのである。そしてこんなやり取りをしながら、手提げ袋に入れてくれたシャツを受け取ろうとレジ越しに俺が手を伸ばすと、「表までお持ちします」と言い、店の前まで袋を持って出て、丁寧に見送りまでしてくれた。俺も「ホンマに大阪に店だしてや」と言いながら気分よく店を離れた。そして家に帰って、手提げ袋の上を留めている店のロゴの入ったセロテープをはがそうとすると、テープの端が折り返していた。これも最近流行のサービスで、セロテープをはがしやすいようにテープを貼るときわざと端を折り返して張っておき爪を使わなくてもいいようにする、というものである。人気のある店っちゅうのはやっぱりすべてに行き届いてるな、と感心した次第ですわ。
2010.02.28
■世界の車窓より(韓国)
バッタもん新シリーズの登場ですが、第2話がいつになるかは全く未定です。とりあえず初回は釜山からソウルへの韓国新幹線です。所要時間はほとんど3時間。何で、関空からソウルに行くより時間がかかるねんと思う。「この電車は、各車両にモーターが付いてないタイプで、先頭の動力車がひっぱるんですわ」と鉄道通の同僚が教えてくれた。それで、スピードが出ないのかとも思ったが、300kmは出るとの噂なので別の事情によるのだろう。まあ、しかし席が狭い。俺は体が大きいので席が狭いのが大嫌いであるがこれもしょうがない。あとで聞くと、日本のグリーン車に相当する上等な客車もあったらしいが、それこそ後の祭りである。で、席に座ってあたりを見渡すと、何となく違和感がある。何でやろう、とよく見ると、車両の前半分は客が後ろ向きに座っている。要は、車両の半分で座席が前向きと後ろ向きに分かれているのである。その結果、写真ではちょっと分かりにくいかもしれんが、ちょうど車両の真ん中の席だけは4人が向かい合わせで座る、いわゆるお見合い席になっているのである。見たところちょうど家族連れのような感じの人が座っていて騒いでいたので、まあ、よかったな(何がエエかわからんが)と思った。しかしこの席は4人グループ以外で予約する人がいるんか、とか、そもそも何で車両の半分で席の向きを変えてるねん、回転式とか可動式に何でせえへんねん、とか色々考えたが、理由がわからん。まあ、色んな事があるから面白いねんやろけどね。
2010.02.25
■ETCの裏わざ
先月の話で申しわけございませんが、昨年に続き伊勢神宮に初詣に行ってきました。昨年行ったのは確か1月の4日で、高速道路のインターも下ろしてもらえず、ひとつ先のインターに回され、そこからシャトルバスで行き来するという結構不便な日に行ってしまったのと、今から思えば、去年はそうやったんや、と思わずにはいられない麻生総理の参拝が時間的に重なったりして、ただでさえ人出が多い内宮はほとんど満員電車の状態やった。この反省から、今年は11日の夕方に行ったんやが、それでも、インターの手前数キロから渋滞していた。片側2車線の走行車線はほぼすべてが伊勢参りの車であるから、入るタイミングを逃し、なかなか走行車線に合流でけんまま、インター手前まで来てしまった。ここから強引に割り込むことは可能やが、完全にズルをしているように見えるし嫌やな、と思っているとき、いい事を思い出した。「そや、このままでええねんや」と一人で声を出して納得し、延々と並んでいるETC専用出口やなしに、ガラ空きの一般出口に向かった。前に知り合いが私有車を仕事で使うときETCで入り、一般出口で出るのに同乗していたのを思い出したからである。それは何でや、というと、領収書を貰うためで、ETCカードを抜いて料金所のオジさんに渡すと、領収書が貰える。会社の経費の精算なんかに使う時に便利なのである。ただ、自分でこの手を使うのは初めてなので、恐る恐るETCカードを渡して「これで、いけるんですよね」と聞くと、オジさんは「ええ、そうですよ、皆こっちきたらエエのに」とETCの長い列を見ながら言った。「それやったら、はよ皆に言うたれよ」とは思ったが、まあ、これも知ってるモンだけが得するっちゅう、ようある話やな、とひとりほくそ笑みながら、効率よく無事お参りをしてきたっちゅうわけですわ。皆さんも覚えとかはったら何かの時に役に立つかもしれまへんで。
2010.02.16
■ タクシー嫌い
あいかわらずやな、とは思うけど、ホンマに京都のタクシーは愛想悪いね。京都駅っちゅうのは京都の玄関口なんやから、もうちょっとマシな対応できんかな、と思うことが多いね。俺もタクシーなんか出来たら乗りたないんやで、高いし、愛想悪いし、何で嫌な思いして高い金払わなあかんね、っちゅうことなんや。こないだは、京都駅から乗るとき、乗り場も空いてたし、俺の順番の時ちょうどプリウスのタクシーが回ってきた。プリウスは3ナンバーやけど、京都では小型車扱いやとどこかで聞いていたので、これはラッキーやと乗り込んだ。そして行き先を「○○町の△△さんへ」と言った。ドライバーは何も反応しないので、「分かります?」と言うと。「分かりません!」と怒ったように答える。「あのね、分からへんのに、何でそんなにエラそうに言うの」と言いたいのをこらえて、「え~っと、○○町へは松原からしか入れませんよね」とこちらが気を使って言うと、「ええ、そうです」とまたエラそうに答える。「何や知ってんねんやったら先言え」とまた言いたいのを我慢して、「松原を入って二筋目を下がってもらって次の右の角です」とものすごく下手に出て説明した。それでもドライバーは、「わかりました」とも何とも言わず、黙って車を走らせた。何が気に入らんのか知らんけど、京都のような国際的観光都市がこれでは、観光立国など夢のまた夢やろね。外国からの観光者訪問数で日本は30位そこそこと何かの番組で言うてたような気がするけど、そら当たり前の話やわ。
2010.02.08
■電車ウオッチ(炊飯器オバサン)
休日の昼間、少し混んだJR新快速に乗っていた。立っている位置は変えることができないくらいの混み方で、俺の背後から結構大きい声で話しているオバサンらしき二人の会話が聞こえてきた。顔が見えないので年齢層は分らないし、見えたところで俺は人の年齢が余りわからないので、結局一緒であるが、子どもが小さいときによく遊んでいた機関車トーマスが好きだの、どうだのという話が聞きたくもないのに聞こえてくる。他に話している人はないので、電車の音よりも大きなどうでもいいような話を無理やり聞かされているのも甚だ迷惑な話であるが、「しょうもないハナシはやめんかい」と怒るわけにもいかない。そうこうしている内に一人のオバサンは携帯電話を取り出し、息子らしき相手と話しかけた。「ああ、○○ちゃん。ちょっと炊飯器の前に行ってくれる。そこのスイッチ押してほしいねん。それでな、12時になったら炊けるから、ご飯適当に食べといてな。それから、ちゃんと勉強しいや。」と実際はもっとどうでもエエような話を車両中に響き渡るほどゴッつい声で話していた。前にも書いたが、サラリーマンとかがこそこそと電話を手で覆って申し訳なさそうにしゃべってるのはまだええが、こんな話を満員の電車内で堂々としゃべれるっちゅうのは一体どういう考えなんやろと理解に苦しむね、俺は。人に勉強しいや、て言う前にあんたが社会勉強せなあかんで。子どもが反面教師にしてくれるのだけが頼みの綱やね。
2010.01.28
■電車ウォッチ(鉄子)
歴史好きの女性を暦女(れきじょ)というらしいが、鉄道好きの女性を鉄子(てつこ)と言うらしいという事は少し前から知っている。俺が滋賀の田舎から京都の高校に通い始めた約40年前、既に高校のクラブに鉄道研究会(通称鉄研)というのがあって、やっぱ、田舎の高校とは違うな、と驚いた記憶があるが、最近も鉄道がブームのようである。昼間にJR新快速の先頭車両に乗ると、運転士の横のスクリーンが空いていて、鉄道マニアでなくとも楽しく運転士越しに景色が見られることがあるが、気がつくと子供と並んで見ていたりすることもある。つい先日もたまたま乗りこんだ先頭車両のスクリーンが上がっていた。結構混んでいたので、ガラスの前までは進めへんな、と思っていると、熱心にガラス越しに電車の行方を見ている金髪女性がいた。日本人が金髪に染めているのではなくあきらかに海外からの旅行者である。連れの男性からみると20代と思われるカップルで、俺のイメージからすると欧米人の女性には珍しくタータンのスカートを履いている。ひょっとするとスコットランド系の女性かもと勝手に想像していた。連れの男性はそれほど興味がなさそうであるがその女性は本当に嬉しそうにガラス越しに景色を観ている。特にトンネルに入った時など、いっそう楽しそうに長いトンネルの出口を探すように観ている。「何かおもろいモンでもあるんでっか?」とこういう時に英語で声が掛けられるとエエやろな、と思うけど、何年も英会話習うててもやっぱり根性がないね。「もう、英語習うの辞めたらどうや、金がもったいないだけや」と家族に言われても反論でけへんはずやわ。
2010.01.22
■電車ウォッチ(サラダ女)
先日、俺がいつも利用しているJRのローカル線に乗っているときの話。休日の昼間であったが席はほぼ埋まっていた。途中の駅から乗ってきた若い女性が通路を隔てた4人掛けの窓側の席に座った。その女性が座ってその4人掛けの席はちょうど一杯である。その女性は俺の右斜め45度くらいの位置になるので、ちょうど目が遭う位置になる。こういう位置関係になったとき、世の多くのおやじは喜ぶのかどうかは知らないが、俺は嫌である。俺の場合、若い女性と目が遭った途端にどうもけげんな顔をされることが多いように思えてしょうがないからである。思い過ごしかどうかも相手に聞いたことがないので分からないが、とにかく、こういうときには顔を合わさないように努めている。そのため、しばらくはうつむいて本を読んでいたのだが、何かの拍子にふっと顔を上げ、その女性を見て一瞬目が止まった。その女性は自分の鞄から、結構大きなタッパを出し、おそらく自分で作ってきたであろう野菜サラダをこれまた家から持参してきたフォークで食べ初めた。そしてその様子を見ている俺には一瞬、一瞥をくれただけで、何事もなかったように食べ続けた。最近は若い男女が通勤・通学電車で飲み食いをしている姿をよく見るようになった。電車で立ちながらおにぎりを食べている女子高生もたまに見る。俺はよほど止むを得ない状況でもない限り、在来線では物を食べないように自分では決めていて、時間の都合でどうしても電車移動中に昼食をとらなければならない時は大きな身体をできるだけ小さくしてコンビニのおにぎりを食べている。シンガポールでは電車での飲食は罰金ということも聞いているし、それは好ましい規則だと思っているから余計である。こういうことは恥ずかしいことなのか、自分が気にしなかったらそれでエエのか、今では別に普通のことなのか何かもうようわからんようになってしまうね。
2010.01.14
■初詣
年末から年始にかけて初めての事がふたつあった。まあ別にたいしたことではないっちゅうのはご察しの通りで、ひとつは、紅白歌合戦を1秒たりとも見なかったこと、そしてふたつめは初詣の参拝者が史上(何の史上かわかりまへんが)最低だったこと。 最近の若い人なら当たり前の事かもしれんが、俺の子ども時代は大晦日は家族そろってこたつに入って紅白歌合戦を見るのが当たり前やった。そんな子ども時代を過ごした俺らの年代(50代ですが)ももう紅白を見ているのは少ないんちゃうかと思う。それにしても、出演者も司会も勝敗も全く知らんし気にもならん、ということころまで来たのは自分なりに時代は変わったな、と思う。で、新年が明けて、30分ほどして、3年ぶりに地元の神社に参拝に行くと、これはまた今までに経験がないほど閑散としている。10年ほど前には雪が降りしきる中30分近く並んでやっと参拝できたのを思うと、いったいどうなってしもたんやと思うような状態である。天気が特別悪いわけやないし、理由が分らん。不況の影響か高齢化のせいかようわからんし、空いてること事態は楽でええけど、後ろに誰もいないような初詣もちょっとそれはどうかと思う。数日後、俺より10年以上若い世代の人と話していると、その人の家では、元日は映画館に映画を観に行き、その後買い物に行くというのが通例らしい。その人が言うのには、生活様式の変化ではないか、ということである。俺みたいに普段は何もしていないものも、初詣くらいはと思っていたが、それもいつまで続くのかとも思う。別に俺が心配する必要はないのかもしれんけど、神社や寺のあり様もかなり変わっていくねんやろなと思う。たぶん、来週行くのでお伊勢さんの様子も見てきますわ。
2010.01.07