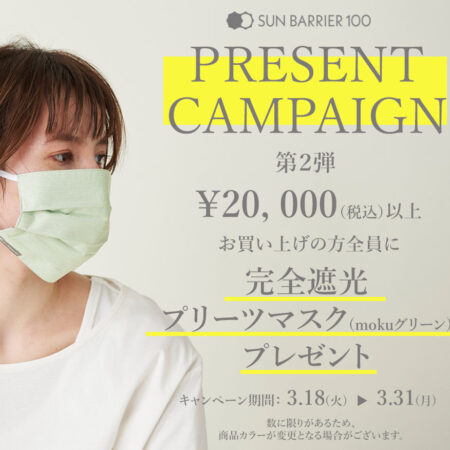2009.6.30 | 岡ちゃんのぐだぐだコラム
2009年1月~6月
■オセアニア紀行(コアラの気持ち)
いつまで続くねん、と一部で言われているオセアニア紀行ですが、一応最終回です。
で、このシリーズ動物シリーズではありまへんが、羊からはじまり終わりはコアラです。俺は、特に動物好きでもないが、上野のパンダも人よりかなり早めに見に行った記憶があるくらいで、珍しい動物にはやはり興味がある。このためシドニーの最終日にコアラを見にいけると聞いてちょっと期待していた。少し前から、オーストラリアではコアラのストレスになるため、抱くことは出来なくなった、と聞いていたので、ガイドさんに聞くと、いくつかの州で禁止しているが全面禁止ではない、とのことであった。どうも俺の情報の取り違えなのか、伝え方の問題なのかよくわからないが、まあ、よくある話である。ただ、我々が行った動物園も抱くことはできない。係員監視のもとで触ることは出来るということらしい。しかし、市内の動物園に行くというのに朝は結構早い。それは開園前に並んでいないと混むからという理由である。日本やあるまいし、と思ったが、開園前一番に駐車場に着いた俺たちのバスの直後には中国人団体客の大型バスが着き、団体客がどやどやと降りてきたのでタッチの差やった。そして一番に動物園に入った俺たちは、檻の中ではなく普通に園内にいっぱいいて愛想よく出迎えてくれるカンガルーをしり目にコアラのコーナーまで急いで行った。コアラ舎では檻の中で何匹ものコアラが木に登りついているが、それとは別に、写真撮影用のコアラが2匹係員に見守られて木の上でユーカリの葉っぱを食べていた。2匹のうち向かって右のコアラは明らかに子供で本当に縫いぐるみのようである。背中は触ってもいいよ、と係員に言われ触ると、ゴワゴワとふわふわの毛の混じったなんともいえない感触やった。なんせコアラは一日の8割は寝ているらしいので、しっかりと起きて、ユーカリを食べながら、カメラの方を向いてくれるコアラにはなぜかガイドさんが一番喜んでいた。やはりガイドさんは案内してきている手前、皆がちゃんとコアラといっしょに写真に収まってほしい、という気持ちが強いのや思う、やはりプロである。コアラ以外にもウォンバット、ペンギン、巨大なクロコダイルなど、あまり見たことのない動物が間近に見られるため、結構な時間を要したが、集合時間の少し前になってもう一度コアラが見たくなり、園内の順路を逆に、コアラの所まで戻った。すると先ほどのコアラは既に寝ていた。器用に木に抱きついたまま寝ている。コアラは寝ていても木から落ちないということで受験のお守りにもなっている所以である。寝ているコアラの実物を見て、起きているコアラとは別にまたイイものを見たなと得した気分になった。コアラは自分で意識しているわけやないやろけど、全く見向きもされないどころか、毛嫌いされる動物は一杯いるのに、幸せなヤツやと俺は前から思っている。人間も動物も外見で判断したらあかん、ちゅうのはタテマエの話で、現実は違うっちゅうのは皆が思っているところである。コアラの気持ちは分からんけど、最高ランクに得な動物であることは間違いないやろね。
(オセアニア紀行一応おわり)
2009.06.30
■オセアニア紀行(中国の席巻2)
若い頃と違って、最近は海外に行っても、免税店で買い物をすることが減ったが、それでも、元(今もか)浪費家としては、やはり気になる。今回もツアーの途中、ある程度時間が取ってあり、シドニー港の近くのギャレリアに寄った。グアムに行ったときも免税店の特にブランド店での中国人団体客の多さに驚いたが、今回訪れた免税店はもうほとんど中国シフトと言っていいくらいの体制であった。ほとんどの階の案内看板は必ず英語、中国語が併記してあり、俺が見た限り日本語の案内看板があったのはバーゲン品のフロアだけであった。客は見たところ、9割以上が中国人で店員はほぼ100%中国語対応可、と見た。ちょっと前のホノルルの免税店(最近は知らない)のように日本語の出来るオバちゃんは皆無である。ウチのツアーのメンバーも中国語で店員に話しかけられ困惑したと言っていたが、ここは一体どこの国や、というくらい中国人と中国語で溢れている。日本人が免税店のブランドショップにいないのは、それだけ消費が成熟したのか、単に景気が悪いのか、たまたま俺の行った時期に日本人が少なかったのかよう分からんが、ガイドさんに話しを聞いても確実に日本人観光客は減っているようである。免税店や定番の観光地が日本人だらけなのも困るが、もうちょっと日本の若者をニュージーランドやオーストラリアで見かけてもええと思うねんけどね。
2009.06.24
■オセアニア紀行(幻の日本酒)
ツアーも終盤になりシドニー市内の日本食レストランに夕食に出かけた。店の入り口には日本酒の一升瓶がずらっと並べてあり、そのなかに有名な新潟の酒「久保田」の千寿があった。ニュージーランド、オーストラリアではビール、ワインが続いていたし、夕食がすき焼きということもあり、席に座るなり「久保田ください」と言った。すると店員は「すいません、あれディスプレーだけなんです」と言う。「何や紛らわしいな」と言いながらも「まあ、ええわ、とにかく日本酒頼むわ」ということで結構皆で冷酒を飲んだ。海外では日本食ブームとか良く聞くが、確かにここの日本食レストランも見渡すと現地のサラリーマン、OLと思われる人が皆、器用に箸を使って造りや鮨を食べている。まともに箸の持てない日本人が増えているのに、シドニーでこんなに普通に箸を使って日本食を楽しんでいるとは想像以上であった。昼間のオフィス街でも、鮨や日本食の弁当を買うのに並んでいる光景も見たし、日本食はブームというより完全に定着しているな、という感じやった。それで、俺は夕食の後は、ホテルに帰って寝るだけやと勝手に思うてたので、実は結構日本酒飲みすぎたんですわ。ところが、レストラン出てから、シドニー湾のナイトクルージングに行くっちゅうことを聞いて、船着場まで何とかフラフラで歩いて付いていったものの、せっかくシドニー港やオペラハウスの夜景が見られるナイトクルージングの往復中もずっと船のデッキのベンチで寝てたんで何にも覚えてないんですわ。ホンマにもったいない話です。そのため、夜景の写真もありません、代わりにレストランの写真を載せときます。(いりまへんか)皆さん、くれぐれも飲みすぎには注意しましょう。
2009.06.15
■オセアニア紀行(スキヤキソング)
シドニー湾の手前にロックス地区という歴史的な建物とともにレストランやショップが並んでいる観光の名所がある。その一角にあるドイツレストランへ夕食を食べに行った。本場には行ったことがないが、ドイツによくあるようなイメージのビアレストランで、女性の衣装もそれ風(どんなんや)である。店のポスターが店内に貼ってあり、年季の入ったオジさんたちが昔ながらの衣装でバンド演奏をしている様子が大きく写っているのでたぶんこの店ではバンド演奏があるのだと思われた。そしてドイツの料理とビールでちょうど我々が盛り上がっているとき、オジさんが3人ほどステージで準備を始めた。やっぱりバンド演奏がこれからあるんやな、と思って、オジさんをよく見ると、先ほど見た店のポスターに写っていたオジさんたちそのものであった。ポスターに写っているときでもかなりの年配に見えたが、ホンマものはさらに年季が入っている。このオジさんたちは一体何十年ここで演奏してんねやろ、と思わせる超ベテランの域である。そして、やっぱりエラいな、と思ったのは、このオジさんバンドはそれぞれの客の国の曲を演奏することである。それでも、選曲をハズしているのか単に客のノリが悪いのか、おそらく韓国の人と思われる家族連れのために演奏した時はその家族はポカンとしているだけであった。この店の団体客は我々日本人だけなので、もともとにぎやかであるが、我々のために演奏されたのは「スキヤキソング」であった。いまさら説明もいらないが、「上を向いて歩こう」は俺が小学生の時の大ヒットソングで、学校の帰りに毎日歌っていたのを思いだす。海外では「スキヤキソング」としてヒットしたことも話としては聞いているが、それこそ海外で生で聞いて、そして皆で大合唱できるとは夢にも思ってなかった。坂本九さんが日航123便の御巣鷹山事故で亡くなったこともこの歌の思い出とともに忘れられないことで、そういう思いもこめて、大きな声で大合唱したが、レストランの一角だけが大盛り上がりで、他のお客さんは意味がわからなかったというか迷惑やったと思う。それでも演奏してくれたバンドのオジさんたちも喜んでくれてたので、まあ、ええやろ、ということにしておいてください。
2009.06.09
■オセアニア紀行(世界遺産3)
このシリーズいったいいつまで続くねん、という話もちらほらありまして最後の訪問都市シドニーに行きます。で、今回のツアー中に見たいくつかの世界遺産の中でも最もベタで、正直そんなに期待してなかったのがオペラハウスでした。シドニーといえばオペラハウスということで、もうあまりにも有名で、一回も行ったことがないのに、テレビの映像や雑誌で何十回何百回と見ているために、自分の中ではもうええや、という気持ちがどこかにあったんやと思う。20年以上F-1に通っている俺に、「F-1なんてテレビで見てたらエエやん」という人がよくいるが、「レースは現場に行くと違うんやで」とよく答えているのと同じで、やっぱり実物の迫力というか、雰囲気というか、青空をバックに、オーストラリアの眩しい日差しの中で圧倒的な存在感があった。真っ白ではない少しベージュかかった生成りみたいな白さが余計にシブく迫ってくるように感じた。何でも現場を踏んでから言わんとあかんな、と反省し、さすが世界遺産やと見る前と全然違う印象になった。でも実はツアーの日程には本来オペラハウスは入っていないっちゅうことで、30分程度しか時間がとれんという、ホンマにテレビ番組の世界弾丸トラベラー状態で、写真撮るのだけで精一杯やった。オペラハウス前の広場みたいなところにはオープンカフェがたくさんあり、ホンマやったらこういうとこでビール飲んでのんびりしたいが、とにかく時間がないので、バスまで急ぎ足で戻った。ちょっとだけでも見られただけよかったけど、まあ日本人の団体ツアーは大体がこんなもんで、ゆっくりしたかったら個人旅行で行かなあかん、ちゅうことですな
2009.05.30
■オセアニア紀行(コミュニケーション能力の問題)
話はメルボルンに戻ります。ベテランのガイドさんのイイところは、何と言っても機転が利くということで、メルボルンでは時間の合間をぬって、市内を走っているタダの市電に乗って移動しましょうということになった。俺は別に電車マニアではないが、日本でも珍しくなった市電で都会の中を走るのはなかなかイイもんである。有料の市電(その方がもちろん多いが)を1本見送って、次にきた無料の市電に乗り込んだ。席がいくつか空いていたが、日本人の美徳というか遠慮のつもりで立ったままでいると、ガイドさんに、「通路に立っていると、かえって邪魔になる場合がありますから、空いていたら座ってください」と言われ、なるほど、と妙に納得してしまった。そして、ツアーに同行している記者の横に座って話しをしていたが、二人の前方の席には、今回のツアーメンバーの中で最高齢71歳で北海道から参加のニシムラさんが一人でおそらく欧米人の旅行者と思われる中年夫婦の隣に座っておられた。そして、しばらくすると、記者のホソダさんは前方を見据え、俺に、「オカガワさん、ニシムラさん何か話されてますよ」と確認を求めるような口調で言った。そんなアホな、と思いながら前方を見ると、確かにニシムラさんは隣りの中年夫婦と談笑しておられるように見える。何やら話をして、3人とも同じタイミングで笑っておられるのがはっきり確認できる。記者のホソダさんも「あれ、確かにコミュニケーションできてますよね」と確信した様子である。電車を降りて、二人で「ニシムラさん、さっき話しておられましたよね、英語できるんですか」と聞くと。「いや、出来ないよ。ジャパン、サッポロだけで盛り上がったよ」と平気でおっしゃる。そして気になった俺は「向こうから話しかけてこられたのですか」と聞くと「いや、俺から話しかけたんだよ」とこれまた平気である。さらに「若者に話しかけてもたぶん返事してくれないだろうと思い、答えてくれそうな中年夫婦に話しかけたんだよ」とまったく感心する話ばかりである。
亀の甲より年の功とはよう言うたもんやけど、これがホンマのコミュニケーション能力っちゅうもんやろな、と教えられる事ばっかりやった。人生もこういう風に年季が入らんとあかんね。
2009.05.22
■オセアニア紀行(中国の席巻1)
最近は京都を訪れる観光客が以前にも増していると聞く。昨年末、京都四条南座の前を歩いている時、聞こえてくる話し声が日本語より中国語が明らかに多くて驚いたことを思い出す。今回、ミルフォードサウンドまでの道程は中国の団体客を乗せたバスと抜きつ抜かれつの競争であったが、たまたま乗り込んだ船の団体客は我々ともう一組の日本人の団体のみであった。あとは、個人旅行の人であったが、その中には中国人の富裕層と思われる中年のカップルがおられた。何故、富裕層と思ったかというと、持っているカメラが日本人の中でも相当マニアか金持ちしか普通は持たない、ライカのデジカメR8を持っていたからである。このカメラは日本では60~70万円くらいはするはずなので、いったい平均的な中国人の何ヶ月分の月収になんねや、という感じである。もともと平均をとること自体があまり意味がないといわれるほど中国の所得格差は大きく、都市部のサラリーマンの平均年収は聞くところによると30万円~800万円とこれでも相当な開きやが、農村部では年収が5万円とか6万円とか聞く。いずれにしてもライカの値段は年収レベルの話であることは間違いないと思う。俺も実物を持っている人はそんなに見たことはない。そういう意味では、日本人の団体旅行より、この中国人カップルの方が消費の成熟度は高いと思う。それでも、船の案内放送は、やはり日本人が多いためか、あるいは日本人は英語を理解しないためか、英語の後で日本語だけが流れる。日本人団体観光客はいつまでも変わらんのか、と思うのと同時に、海外で感じる中国人の人的・経済的なパワーからすると、もうすぐこのアナウンスには中国語が加わり、そしてその次には日本語のガイダンスがなくなってしまうんちゃうか、とふと思ったわけですわ。強ち妄想やとはいえんと思いまっせ。
2009.05.16
■オセアニア紀行(ガイドの鑑)
クイーンズタウンからミルフォードサウンドに日帰りで出かけるには、道路と時間が限られているため、ほとんどのツアーバスが朝早くから一般道を日本の常識では考えられないくらいのスピードで先を争って走っている。一般道でも100km規制のところがあるのは前にも書いたが、さらに、日本ならまず30kmか40km規制になるのは間違いないような結構急なコーナーでも75kmという表示が多く見られる。バスはもちろん乗用車でもシロートではまずそんなスピードでは回りきれるハズがない、と思えるコーナーで「回れるもんなら回ってみよ」みたいな表示にしか思えんとこがある。まあ、そんな道を競争しながらも、途中、原生林や山や沼など、風景の良いところでバスを止める定番の場所がいくつかある。そのなかで、道路わきの駐車場にバスを停めて、駐車場の中をひょこひょこ歩いている野生の珍しい鳥(名前は忘れた)が見られるスポットがある。野生の鳥はもちろん触ったり、追いかけてはいけないので、バスを降りて写真を撮っていると、少し離れたところで、欧米豪人(ややこしいな)と思われる若者グループの一人が鳥にお菓子を与えはじめた。当然、鳥はみなそっちに集まっていくので、若者グループは大喜びであるが、「菓子はあかんやろ」と思いながらも、いかつい身体つきの外国人の若者に文句を言うほど根性も語学力もない。その様子に気づいた女性ガイドのヨネ○さんは血相を変えて若者のところまで行き「鳥に餌をやっちゃダメよ」みたいな事を言った。菓子を与えていたその若者は、ガイドさんを睨みつけ、不気味な半笑いで、「なぜ、駄目なんだい」みたいに反論してきた。ヨネ○さんは、ひるまず「鳥に餌を与えることは禁止されているのよ」とさらにキツい口調で訴えた。すると若者は「ああ、そうかい」みたいに諦めて、バスに帰っていった。何と、その若者は若者グループの乗っている中型バスのドライバーであった。そして悪びれずに我々にバイバイと手を振ってバスを発車させた。「人に注意をしないといけない立場の人なのに何てことよ」とヨネ○さんは、まだ、怒りが収まらない様子でボヤいていた。ガイドとしてはまだベテランと言うには気の毒なくらい若いガイドのヨネ○さんであるが、そのプロ意識に感心するとともに、いつもの事ながら自分の根性の無さにホンマに情けのうなってしまいましたね。
2009.05.08
■オセアニア紀行(バンジーその2)
我々の仲間が飛ぶ順番が回ってきた。バンジーで飛び降りる先は川であるから、あらかじめジャンパーの希望を聞いてロープの張りを調整するらしい。つまり、ロープが伸びきった時に、頭や体が川に入ってもいいか、嫌かなどで、(1)川に浸かるのはイヤ(2)頭くらいならいい(3)上半身浸かってもいいとかそういう聞き方をされるらしい。ウチのメンバー4人はせっかくだからということで全員上半身ハダカになり、腰まで川に入る覚悟で飛びこんだ。しかし、まあ60m以上も飛び降りるロープの張りを調整するのは難しいのであろうか、日本人は体重が軽いからであろうか、4人とも川に浸かることはなくビヨーンとロープに戻されていた。で、どうやって回収されるかというと、何回かロープにビヨ~ン、ビヨ~ンと翻弄され揺れが収まると、川辺で待機しているゴムボートが逆さまに吊るされているジャンパーを頭からゴムボートに下ろし、岸まで運んでくれるという段取りである。ジャンパーが飛び降りる橋と同じ高さには渓谷を見下ろすように見学台があり、そこから観客が見られるようになっている。ボートに回収されたジャンパーは専用の階段を下から上がってくるのだが、その途中にも踊り場のような見学台がありそこからは見上げられるようになっている。女性ガイドのヨネ○さんは、自分が誘った手前という事もあるのかどうか、川から上がってくる4人を向かえるため上着を持って、階段を途中まで下がったその見学台から心配そうに見上げている。俺なんかは、飛び降りる橋の上を歩くだけで腰が引けてしまうくらいで、女性や子供やカップルがいかにも楽しそうに飛び降りているのが全く信じられない。そして後から聞いた話だが、飛び降りるために上半身裸になったツアーの添乗員ワタナベさんを見て、ガイドのヨネ○さんは一言「ワタナベさんて結構ヤセてるんですね」と冷静に言うてたらしい。さすがというか何というか、こういう場面での目の付けどころに俺は何故か感心してしもたね。
2009.04.28
■オセアニア紀行(バンジーその1)
クイーンズタウン郊外で用事を終えた帰り、女性ガイドさんから「バンジージャンプ発祥の場所が帰り道にあるので、せっかくですから寄りませんか」と提案があった。夕方とは言ってもまだ時間が早いし、ほとんどのメンバーが興味を示し、行こう、行こう、ということになった。いまではすっかり定着したバンジージャンプだが、もともとはこのクイーンズタウンに近いカワラウ川にかかる橋から飛び降りたのがはじまりらしい。道沿いにあるバンジージャンプ場(というのかどうかわからないが)は結構近代的な施設であるが、目の前に飛び込んできた高さ60m以上の橋とはるか下に流れている川の流れを見ただけで俺なんかはビビッてしまう。途中、バスの中で「やっぱ、誰か飛ばんとあかんね」と冗談で言っていたつもりやったが、何とウチのメンバーから4人も飛ぶことになった。ウチのメンバーの前に飛んでいる欧米人(豪州人かな)はいずれも経験者みたいで、一様に楽しそうに気分よく飛び降りている。ウチのメンバーが飛ぶのにはもう少しかかりそうで、高い見学台みたいなところに立っているだけでトイレに行きたくなり、建物の中のトイレに行った。そこでトイレの表示を見て、さすがにシャレが効いているなと思って、写真を撮った。こうなると女子トイレはどんな看板やろ、と気になり、女子トイレのドアーの前まで行きカメラを構えていると、背後の通路からトイレに向かってくる女性の声が響いてきたので、あわててカメラをしまい逃げるようにその場を離れた。トイレのドアーの写真を撮っても別に違法ではないやろけど、どう考えても日本人の変なおっさんが女子トイレのドアーをカメラで撮っている姿は異様やろうと思う。いきなり悲鳴をあげられるかもわからんのでホンマに慌てた。まあ、女子トイレの看板がどんなんやったかは、謎のままの方がええかもわかりまへんな。
2009.04.22
■オセアニア紀行(親切な店員)
夕食後ホテルの部屋に帰ってからビールが飲みたくなり、クライストチャーチの夜の街に一人で出た。日本のように便利なコンビニがあるわけでもないが、ほとんどの店が閉店している商店街でも一応コンビニのような店があることはある。ホテルから出て一番初めに見つけたコンビニで「ビールはありますか」と聞くと、「無い」という。日本でもビールを置いているコンビニと置いていないコンビニがあるので、こっちもいっしょかなと思い、別の店を探したが、夜の9時くらいではもうほとんどの店が開いていない。しょうがないので、あきらめて先ほどのコンビニの前を通ってホテルに帰ろうとするとコンビニの店員が店の前でタバコを吸っていた。さっきもあまり愛想がよくなかったし、まあ、絡まれることは無いだろうとは思いながらも目を合わさないように店の前を通り過ぎようとした時、その東南アジア系のニイちゃんが「ビールはあったのかい」みたいな事を言った。俺は「いや、無かった」と答えると、「すぐそこに酒屋があるだろう」と言うのである。コンビニの手前5軒くらいには確かに酒屋があったが店の前を先ほど通ったときは既にシャッターが閉まっていたので、「いや、閉まっている」と答えた。すると「まだ、人がいるはずだ」と言いちょうどシャッターから出てきた店長と思われる人に「お~い、この人がビールが欲しいと言ってるから売ってやってくれ」みたいなことを大声で叫んだ。店長らしき人は、分かったというようなポーズで降ろしたシャッターをもう一度上げかけたので、俺はあわてて礼をいい、酒屋まで走って行った。日本では24時間いつでもビールが買えるのが当たり前でさらにそのために人とのコミュニケーションをとることも必要ないが、何でも便利になればエエわけでもないな、としみじみ人の親切さが身にしみたっちゅうわけですわ。
2009.04.16
■オセアニア紀行(クライストチャーチ)
話はオーストラリアまで行ってしまいましたが、ちょっとニュージーランドの小ネタに戻ります。(というか全部小ネタですけど)。今回のツアー案内をもらったとき、オーストラリア・ニュージーランドの地図と空路が書いてあり、ニュージーランドへの直行便の絵になっていたが、出発直前のスケジュールでは成田からシドニーに入り乗り換えて、クライストチャーチに飛ぶ行程に変わっていた。帰りがシドニーからなので、一般的なツアーではそれが通常やと思うが、まあ、結構いい加減な旅行社であることは間違いない。それはそれとして楽しみにしていた初めてのニュージーランドで、最初に訪れたクライストチャーチは南島では最大の都市でニュージーランド2番目の都市である。と言ってもせいぜい38万人くらいの小さな街であるし、ガーデンシティーと言われるように公園や庭園がキレイな想像通りのイイ街であった。名前の通り、教会を中心に開かれた街で、観光客やバックパッカーと地元の生活者やサラリーマン・OLがいい具合に混在している。大橋巨泉のOKギフトショップもあるくらいなので日本の観光客も多いのだと思われる。街には路面電車が走っており、写真を撮っていると電車の先頭に見慣れないものが付いていた。遠目では分からなかったが、よくみるとベビーカーを付けているのだった。まさか広告ではないだろうから、電車に乗る客のベビーカーを付けているのだと思う。ハワイではバスの前に自転車を載せて走っている光景をよく見るが、ベビーカーを電車に付けているのは初めて見た。俺が京都の高校に通っていたころはもちろん市電が京都の街の中を縦横に走っていたが、自動車の交通の邪魔になるとか何とかでもう相当前に廃止になってしまった。京都の市バスにベビーカーで乗るのは相当困難やろなというのは想像するに易い。まあ、色んな条件の違いはあるやろけど、日本でバスに自転車乗せるとか市電にベビーカー乗せるなんて事はまず実現しそうに無い話やね。
2009.04.07
■オセアニア紀行(バングラデシュ)
翌朝一番の飛行機で届くはずのラゲージは悪い予感通り朝には届かなかった。その日は今回のツアー中、唯一スーツ着用を義務付けられていた用事がある日で、皆その日のためだけにラゲージにスーツを入れて来たのであるが届かないものはしょうがない。通訳兼ガイドさんにはくれぐれも先方さんに事情を説明して、と頼みながらガイドさん以外は全員前日と同じ普段着のままで大企業の訪問に出かけた。説明に当たってくれた会社の代表者は「皆さんの荷物は中国まで行ってしまったんでしょうかね」などと欧米人(ではなく豪州人か)のビジネスマンらしいジョークでちゃんと対応してくれた。そして何とか昼間の用務を終え、夕方ホテルに帰るとまだラゲージは届いていなかった。まあ、海外ではよくある事とは話では聞いていたが、自分自身の経験は初めてである。しかも翌朝はシドニーへ移動であるから、今日ラゲージが届かなかったら、明日も着の身着のままである。こうなると心配性の人間はする事が同じで、俺が一人で街を適当に歩き回ってたどり着いたセーフウェイだったか何だかのスーパーマーケットの下着売り場には同じツアーの先客が3人いた。うち一人は楽観的な人で「たぶん今日着くと思うから俺は買わない」と言っていたが、俺はそういう気にはなれないので、結局3枚組のトランクスとTシャツ1枚を手に取った。そしていつもの癖で製造国を見ると、トランクスは予想通り中国であったが、Tシャツはメイドインバングラデシュと書いてある。バングラデシュといえば貧困国のひとつくらいしか知識が無いが、そういえば最近は縫製業が増えているとは聞いている。俺がこのTシャツを1枚買うことでバングラデシュの経済に貢献するのやろか、それとも低賃金でこきつかう経営者に加担するのやろかどっちやろ、としばらく考えたが、とりあえず今は財布の負担を考えようと一番安いそのTシャツを買った。しかし、オーストラリアまで来てバングラデシュの事を考えるとは思うてなかったな、と頭の中で考えながらホテルに戻ると、ちょうどロビーにラゲージが届いたところやった。何でも考え過ぎるとこうなるっちゅう見本やけど、Tシャツが無駄になったとは思わんようにしたいね。
2009.03.31
■オセアニア紀行(春節)
結局3時間以上遅れた飛行機がメルボルンに着いたのは夜の10時を回っていた。せめてもの救いはベテラン(といっても俺よりは断然若い)の男性ガイドが出迎えてくれたこと。プライベート以外で海外に行く時は大抵現地ガイドさんが付いてくれる事が多いため、ガイドさんの良し悪しでツアーの印象が決まってしまう。そういう意味では初めてのオーストラリアで初めてのガイドさんが当たりでよかった。そしてやっとホテルに着いたら11時を回っていた。しかし、ラゲージがないため、着替えることも出来ないし、こんな時間に店は開いてないので、着替えを買いに行くこともできない。さらに晩御飯もちゃんと食べてないので、腹が減ってきた。夕食に予約していたレストランは既にキャンセルをしている。それでも添乗員が色々当たってまだ開いている中華料理店を探してくれた。ホテルの近所で歩いていけるところとかで、他の店はすべて閉まっている真っ暗な通りを歩きながら「ホンマにこんな時間に開いてる店なんかあるんかいな」と言いながら店に着くと、そこは夜の11時半を回っているのにドアを開けると店内は満員で大宴会状態やった。1階はすべて満席で案内された2階も半分くらい席が埋まっていて、小さな子供連れもいる。よう考えたら、中国では春節(旧正月)の時期で中国系の店だけは遅くまで賑わっているっちゅうことやった。紹興酒もウマかったし、しばしは荷物の届かない不安も忘れていたが、ホテルの部屋に戻って着替えの無いことを思い出した。俺はパジャマがないと寝られないので、どこへ行くときも家で着ているパジャマを持って行くのやが、今回だけはどうしようもない。昼間に着ていた服のまま寝るのも嫌なので、結局パンツ一丁で寝ることにした。季節が日本の反対の夏で良かったな、と思うとともに、今度から機内持ち込みに着替えとパジャマ入れとこうと真剣に考えてしもたね。
2009.03.27
■オセアニア紀行(ヒアリングの問題)
クイーンズタウンからオーストラリアに行くのにはクイーンズタウン空港が近い。何せ、街から10分くらいのところに空港がある。ただし、ローカルなためメルボルンには週末は便がないとの事で、オークランド経由で行くことになっていた。そのオークランド空港では降りたところで失礼ながらガイドとはとても見えないごくフツーのオバさんが待っていた。ここは一旦空港の外へ出て、バスに乗って国際線ターミナルに行くようになっていてちょっとややこしいため、乗り換えのためだけにオバさんガイドが付いてくれたようである。そしてこのオバさんガイドは搭乗手続きを終えるとさっさと帰ってしまった。しかし、ガイドがいない時に限ってトラブルは起こるもので、飛行機が何だかんだ言って3時間遅れになってしまった。こうなると誰かを悪者にせんと気が済まんメンバーの一人は「あのオバはん疫病神やったな」とぼやき始めたが、もちろんオバはんのせいではない。そうこうしているうちにアナウンスが何回も入り、搭乗口付近のひとが何やらざわざわとなった。俺が聞き取れるのはラゲージがどうとか、明日の朝がどうとかという部分だけであとはさっぱり分からない。添乗員も含めウチのメンバーのヒアリング能力はしれているため、「どうやら飛ばないらしいで」という事になり、添乗員はあわてて地元のエージェントに電話し、急遽今夜の泊まりを手配し始めた。しかし、人の動きがあるわけでもなく、もう一度確かめに行った添乗員は他の客と何やら話している。そして我々のところへ戻ってきて「分かりました、飛行機は飛ぶけど、ラゲージが載らないため、荷物だけ明日の朝になるということですわ」と説明してくれた。話をしていたのは親切な地元の乗客で分かりやすい英語で説明してくれたらしい。まあ一安心といえばそやけど、何言うてるか分からんちゅうのはホンマに話にならんね。つくづく英語の能力は大事やと思いましたな
2009.03.16
■オセアニア紀行(世界遺産2)
今回のツアーに出る前、オプショナル・ツアーの中でどうしても決断できなかったものがある。セスナ機で世界遺産のマウント・クック山頂や氷河を遊覧するというエアー・サファリというやつである。何が怖いって、俺は高いとこが大いっ嫌いなので、あんな小さな飛行機でフラフラと飛ぶことはちょっと想像できなかった。しかし、現地に行って下からマウント・クックを眺めていると、これはやっぱり、いま行っとかなあかんな、と一大決心し現地で申し込んだ。飛行場につくとそこには管制塔どころか管制小屋らしき建物も見当たらず不安になったがもう遅い。天気が悪くなりそうだから早く行こうと言われ、急いで小さなキャビンに乗り込んだ。そして、ウチのツアーメンバー5人が乗り込んだ小さなセスナ機はユルユルと滑走路脇を走り出した。草原の中には舗装された決して長くはない滑走路が1本あるだけで、滑走路の端までいくとセスナはUターンし、エンジン音を上げた。窓から覗くと俺の真下で小さなタイヤが回っている。大きなジェット旅客機はタイヤがいくつかパンクしても全く平気ということを知っているので全然不安はないのだが、このセスナには2つしかタイヤはない。「今パンクしたらどないすんね」などという俺のヘタレな思いとはもちろん関係なく機体はフワッと持ち上がった。眼下に見える氷河から何本もの青い筋が流れこんでいる川を左旋回で上昇しながら越える時、リチャード・バックの「イリュージョン」の中の農場の上を飛ぶシーンを何故か思い出し軽い感動を覚えた。しかし、この感動は長くは続かず、高度が上がり山頂近くになると機体がエアーポケットに入ったように時折フッと垂直に落ちるような動きが多くなった。俺は余裕をもって氷河を覗き込んでいるように見せていたが、実は軽い飛行機酔いの状態まで襲ってきて恐怖と酔いでヘロヘロになりかけていたのである。それでも全部で40分程度の飛行なので、何とか持ちこたえられた。他でも経験のある同乗者は、「今日の揺れなら大したことは無い」と言っていたが、俺には十分怖かった。しかしまあ、何でも経験はするもんやとは思うが寿命も縮めてるような気がするな。
2008.03.09
■オセアニア紀行(世界遺産1)
今回のツアー中、いくつかの世界遺産を観光することが出来た。なかでもマウントクックとともにスケールがでかかったのはミルフォードサウンドである。氷河が削りとった壮大な地形は本来フィヨルドと言うべきところを最初サウンド(入り江)と言い間違ったらしいが、今日まで名前は訂正されずそのままでええやん、みたいな事でずっとサウンドと呼ばれているらしい。この辺もまた、大雑把と言うか鷹揚でええなと思うところですな。そしてその壮大なフィヨルドの中を観光船でクルーズするのやが、この船の中での幕の内弁当のマズイこと。カウンターではサンドイッチとかスナックとかビールを売っているので、俺はデッキでビールとサンドイッチで風に吹かれてる方がよかったな、と思うくらいやが、日本人のツアー向けの幕の内っちゅうのがたぶん長年続いた定番メニューなんやろね。グアムでサンセットディナークルーズに行った時の船の中の夕食もとてもディナーとは呼べんようなもう何十年前のメニューやというくらいのショボさやったけど、この時と変わらんくらい情けなかった。こんな遠いとこまで来てわざわざまずい幕の内食いたなかったな、ちゅうのが正直なとこやが、俺も含めほとんどが一見さんやろし、その不満はなかなか届かへんねやろなと思う。日本人の団体客だけが一箇所にあつまって弁当食うてるのも何か違和感あるし、もうこういうスタイルは卒業した方がエエと思うね。
2008.02.28
■オセアニア紀行(女王の街2)
海外に行くと必ず探すのが靴である。俺の足のサイズは28.5cmから29.0cmで特に革靴を国内で探すのに苦労する。その点海外に行くと大きいサイズはいくらでもあり、また、日本では結構高いブランドが現地では安く買えるため一石二鳥である。今回も捨ててもいいような靴を家から履いていき、現地で履き替えるつもりだった。ところが昼間は本来の用事があるし、夕方ホテルに帰るのがちょっと遅めになるとほとんど店はあいてない。何せ飲食店以外の店舗は夕方6時くらいでほぼ閉まってしまう。開いているのは日本人相手のみやげ物店くらいで、しかも現地スタッフは5時できっちり帰ってしまうらしいので、日本人のスタッフだけが遅くまで残っている。それでも空いた時間を何とか工面して街の靴屋さんを何軒か回った。さすがにトレッキングの本場であるからトレッキングシューズや登山靴は豊富に揃っているがリゾート地ということもあってビジネスシューズはほとんど見あたらなかった。ウオーキングタイプの靴はいくつかあり、その中で気に入ったものがあったので、小さいサイズを聞いてみた。これは、そもそも日本ではありえないことで、俺の場合、日本ではいつも「大きいサイズはありますか?」と聞くのが当たり前になっているが、クイーンズタウンの街の靴屋さんの見本は12インチ(イギリスサイズなら約30.5cm)で俺には大きいので「これの小さいのあります?」と聞かないといけないのである。すると店員はパソコンで在庫を確認し、「これより小さいのは無い」と申し訳なさそうに答えた。まさか俺の足が入るような小さいサイズがないとは夢にも思わなかった。結局底がツルツルになった靴を履いて移動を続けることになった。子供の頃よく「バカの大足、マヌケの小足」と家で言われたが、そうすると、俺は日本ではバカでニュージーランド゙ではマヌケになるっちゅうことやね。
2009.02.23
■オセアニア紀行(女王の街1)
スーパーマーケットのクイックレーンとともに、海外では常識でも日本にほとんど無いものの代表として路面のバンプがあるといつも思っている。バンプとは路面に人工的に作った盛り上がりのことで、路面と同じアスファルトを畝のように盛り上げたものが多いが、路面にゴムを後から付けたタイプも見たことがある。そういうたら何やけど、上海のホテル入り口付近でさえちゃんとバンプを設けて車のスピードを落とすようにしてるのに、日本ではなかなかお目にかかれない。今回、女王が住むにふさわしい街と言われるクイーンズタウンの街中でもこのバンプと標識を見つけた。ここのバンプはこんもりと盛り上がったタイプではなく、比較的広い範囲で段差をつけているもので、写真を撮っておいた。数字で15と書いているのは速度制限が15kmということで、こんなとこ30kmで通過したら車の中の人は屋根に頭を激突するくらい飛び上がると思う。ニュージーランドは街からちょっと郊外に出ると、一般道がいきなり100km制限と目を疑うような標識が目につくようなところで、15kmから100kmとメリハリのある速度制限でしかも皆それを守ってるところがエラいと思う。ほとんどの人が守らんような40km制限がいたるところにある国とはだいぶ違うと思いましたね
2009.02.20
■オセアニア紀行(羊の悩み)
誰もアテにはしてないとは思いますが、長らくアップをサボっておりまして申し訳ございません。とある理由でニュージーランド・オーストラリアに行ってましてその間更新が出来なかったというわけです。以前英語を習っていたニュージーランド人の先生は話の端々にオーストラリアと一緒にしてもらっちゃ困るみたいな事をよく言っていた記憶があるので、心外な人もおられるかもしれませんが、とりあえずまとめてオセアニア紀行としてしばらく続けたいと思います。まずは、ニュージーランドですが、以前から羊が人間より多いと聞いていましたが、これは確かに都市伝説ではなくホンマの話です。でも以前は人間の26倍いたのが今は10倍っちゅう話です。まあ、理由は色々あるみたいですが、フリース等の新素材の台頭で羊毛製品が減ってるっちゅうのは確実にあると思いますな。俺なんかももうウールのセーターとか持ってないし、仕事用のスーツなんか1万円以下のものしか買わんことにしてるし、俺らの子供の頃みたいにウール製品の高級感はもうほとんど無いと思うね。最近は羊に変わって鹿とかヤギとかが増えているみたいで、羊はどうも手間がかかる割に値段が良くないが鹿は捨てるところがないとかヤギの方が付加価値が高いとか聞くと、今の世の中、ここでも経済効率の悪いモノは消えていく運命にあるのかと思ってちょっと羊が可哀想に思えてきた。俺がひつじ年やから、という理由だけやなしに、羊が動物園や聖書の中だけの生き物にならんようにと願うところやね。
2009.02.19
■輸入車偏見
最近は外車とは呼ばないで、輸入車と表現することが多いみたいやが、俺みたいに昭和30年代生まれになると、田舎では一部の金持ちしか自家用車を持っていなかった時代なので、「外車」という響きには特別のものがある。しかし、最近では外車改め輸入車と言っても特別高価なものでもなくもっと高価な国産車はいくらでもある。しかも何回かこのコラムで書いたように俺は、もう10年以上中古輸入車にしか乗ってない。今の車も47万円だったか57万円だったか忘れてしまうほどの値段のフォルクスワーゲンである。でも、こんな時代でも俺の住む滋賀の田舎では輸入車に対する偏見はまだ生きている。自動車部品販売大手のAバックスやRスター、あるいは県内大手の安売りガソリンスタンドでは輸入車は一切触ってくれない。オイル交換やタイヤの交換もダメである。昔、フォルクスワーゲンと日産が提携して日本の工場で作ったVWサンタナという車に乗っていた時も「これは日産で作ってるんやで」と説明しても断られた。VWゴルフの時も断られ、「これより高い国産車はいくらでもあるやん」と言うのが精一杯の抵抗やった。つい先日も、スタッドレスタイヤがパンクしたため、家に一番近いスタンドまで行き、ひょっとしてと淡い期待で車を見せると、「すいません、ウチ外車はタイヤ交換できないんで・・」と瞬時に断られた。「それなら、ここで自分でタイヤ外すので工具だけ貸してくれる?」と聞くと。「工具の貸し出しはしてないんです」とこれも断られた。「場所は借りてもええの?」と聞くと「隅の方なら」というので、スタンドの隅で一人でタイヤを外して、タイヤのはめ代えだけしてもらい、また、自分で車に入れた。昔は京都や大阪市内の駐車場では「3ナンバーお断り」というところが結構あった。今や、軽以外では5ナンバーの国産車は数えるほどしかない。それと一緒で輸入車というだけで、触らぬ神にたたりなしみたいな考えはほとんど原始時代の考えとしか言いようがない。50万そこそこの中古外車と500万円をはるかに超える某国産車のどっちが気い使うかは幼稚園生でもわかるっちゅうねん。こんなこといつまでやってんねんやろね。
2008.01.26
■ネットの功罪
俺の家は商店街の中にあるんやが、何せ田舎の商店街であるからどの店もほとんどが地元の客相手である。ウチから数軒行ったところに年寄りの夫婦二人だけで営業されている肉屋さんがあるが、実はここの肉は安くて旨いのである。中でも特に豚肉が安くて旨いのでこれだけを買いにくる地元のお客さんも多い。ところが昨年の年末からこの肉屋さんに客が殺到するようになり、周りの店が迷惑駐車で商売が出来ないほどになった。肉屋さんの隣は写真屋さんであるが、店の大将によると、年末のある日、自分の店の前に何台も車が止まっていたので、「今日は客が多いがな」と喜んで店に入ったら中には客が一人もいなかった、とのことで、多い日は2時間待ちとかで、狭い肉屋の店内に何重もとぐろを巻くように客の列が出来ているらしい。県内の別の市や三重県などからも来ているようで、お年寄りの夫婦はフラフラになりながら肉を切って、量って、レジを打っておられる。この店の奥さんは2年前にも誤って自分の指を切り落としてしまわれたことがあり、あんまり商売が流行りすぎるのも心配なるくらいである。で、何で急に流行ったかというと口コミに加えてブログで誰かが書いたらしい。特に子供がスポーツ少年団に入っているような父兄の口コミが最初だったらしく、まとめ買いの量も半端ではないので、よけいに品薄になったらしい。しかもこの店は前からそうなんやが、肉を量っていて在庫がなくなると、足りない分は一ランク高い肉をまぜてしまうという何ともアバウトというか、太っ腹なところがあるので、これがまた人気の秘密でもある。京都の有名ラーメン店で、常連さんが食べられなくなる、ちゅう理由で取材お断りの店が結構あるが、この気持ちもよう分かるわ。俺なんかもアテにしてた豚肉食えへんことが増えてしもた。しかし、人の口とブログは止められんし、ほんまに夫婦が心配や。まあ、俺のコラム読んでる人はほとんど無いので安心やけどね
2009.01.22
■自責の念
正月の休み中に梅田のヨドバシカメラで買い物をし、地下通路からJR大阪駅への階段を上がろうとしたら、階段の途中に人だかりがあった。見ると階段途中の踊り場付近で中年の女性が仰向けに倒れていた。顔は蒼白で動いていない。ちょうど一人の若い女性が「だれか救急車を呼んでください」と叫んでおり、別の男性が倒れている女性の耳元で「聞こえますか、聞こえますか」と声をかけている。そのまわりには何人もの人が取り囲んでいるが、ただ、様子を見ているだけである。そういう俺も、一人で両手に買い物荷物を持ち、電車の時間がギリギリだったため、すでに何人かが手当てを始めているからいいか、と自分に言い訳をしてその場を通り過ぎた。改札を抜けながら早く救急車の音が聞こえてくれと思っていたが、結局、電車に乗るまでに救急車の音は聞こえず、やっぱり何か手伝いをすべきやったな、とその後もずっと悔やんでいる。俺は仕事の関係で救命救急の講習も以前に受けているし、昨年はAEDの講習も受けた。あとから色々考えると、倒れていた女性は一人で外出中であり、世話をしていた女性と男性は通りがかりの人に違いないと思えてきた。それなら尚更の事色んな手伝いが出来たかもわからんなと、今頃考えても遅いのである。先進国では一般市民の多くが救命救急の講習を受けていると聞くが、俺みたいに講習を受けていても何だかんだ自分で理由をつけて通りすぎているようでは全く意味がないね。正月早々自分に対して超お怒りや。
2008.01.19
■マニアックな参拝客
日本人の典型で、正月番組でビートたけしが伊勢神宮に参るのを観て、翌日にお伊勢さんに参ってきた。江戸時代では一ヶ月余りもかかり、一生に一度と言われたお伊勢参りも、ウチの家からは伊勢自動車道も出来たおかげで今は2時間弱でいける。1月4日までは交通規制で伊勢神宮内宮の最寄インターでは降ろしてもらえず、県営のアリーナ駐車場に車を停めてシャトルバスで行くというパーク&バスライドというしくみになっている。ここのシャトルバスは運転手の愛想や係員の応対もよく、また市内の道路はバス専用レーンを走るように出来ており、うまく考えられているなと思った。内宮の境内は予想以上に人は多く、何やら報道陣も多いし物物しい警備やなあ、と思ったらちょうど麻生総理が参拝にくるとのことであった。参道をロープで半分に区切られ、ただでさえ人出が多いのに通勤ラッシュの状態で少しづつしか進めない。それでもというか、さすがにというか、周りで話をしている若いカップルの会話を聞くともなしに聞いていると、「式年遷宮(しきねんせんぐう)は20年に一度や」とか「次は平成25年やな」とか若いのにマニアックな話が多い。そうかと思うと、ロープの通行規制に腹をたてて宮内庁の職員や警備の警察官に「こんなに迷惑をかけて、皆に謝れ」とうなってるオヤジもいる。皆に謝れて、どんだけの人間に謝れっちゅうねん、と思わず突っ込みをいれようと思ったがもちろんやめといた。まあ、こんなオヤジはお参りしてもまずご利益はないやろね。この国は結局大人が悪うしてるっちゅうのは結構あたってると思うね。
2009.01.13